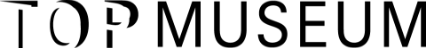学芸員コラム

木村伊兵衛「那覇の市場」 1935年



1988年から15年にわたって続けられてきた当館のコレクションには、古今東西の優れた写真作品が23,000点以上収蔵されています。その特徴として、約70%が日本人による作品であるということがあげられます。これは幕末に写真術が渡来してから今日に至るまでの日本の写真の歴史と現在を体系的にたどることができるということでもあります。それと同時に、世界の写真史を理解するために海外の美術館に対しても誇りうる写真史上重要な欧米の作品も数多く収蔵しています。今回の連続4回にわたる写真展は写真が私たちの生活や思考にどのような役割を果たし、影響を与えてきたかという切り口で、東京都写真美術館がこれまで収集してきた作品の魅力をご紹介していきます。
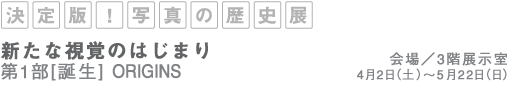
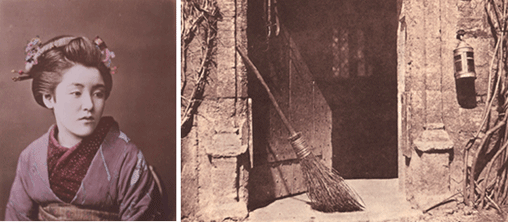
左)STLLFRIED & ANDEREN スティルフリード&アンダーセン"Views & Costumes of Japan"よりPortrait of Woman (女性像)1877-85年
右)TALBOT, William Henry Fox ウィリアム・ヘンリー・フォックス タルボット世界初の写真集 “The Pencil of Nature(自然の鉛筆)”より The Open Door(開いた扉)1844-1846
ルネサンス期、自然科学への興味の高まりから【カメラ・オブスクラ】の諸原理が衆目を集めました。色彩が鮮やかに照射される映像は世界を瞳で把握する手段として、第一の視覚【裸眼】に次ぐ第二の視覚と呼べるほど西欧の社会に浸透しました。第三の視覚【フォトグラフ】は19世紀前半のヨーロッパに誕生しました。それは、これまでとは全く異なった視覚経験を人間にもたらすことになりました。人物、風景だけでなく、微小なものから極大なものまで、ダゲレオタイプの銀板、ダイレクト・プロセスによる紙など、さまざまな発明によって世界に定着していったのです。これまでの映像写真が「動く」物でしかなかったのに対して、【フォトグラフ】の映像は「止まった」ものでした。これによって、これまで裸眼とカメラ・オブスクラで動画画像しか捉えられなかった人間の視覚は大きく変わっていきました。1844年~46年にウイリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット(英)が出版した世界初の写真集「自然の鉛筆(The Pencil of Nature)」には建物やレース編み、植物、演出を加えたアート作品が収められ、写真によって様々なことが出来るようになったということが雄弁に語られています。また、今でこそ自分自身の画像(肖像)を持つことは当たり前の時代になりましたが、当時は王様や貴族のみが持てる貴重なものでした。 それが写真の発明によって、一般にもどんどん普及するようになったわけです。“見知らぬ国の風景をこの目で見られる”ということもあるでしょう。まさに「世界を手の中にできる時代」になりました。一方、日本では、1848年に「写真器」が輸入された後、1854年にはペリーとともに初めて写真師が訪れ、多くのイメージ・ハンターが幕末の日本へと渡航します。やがて江戸や横浜、長崎などを中心に日本人写真師が登場します。当時、「ポトガラヒー」(photography)と呼ばれた日本の写真は、肖像、風俗、風景とさまざまに展開し独自の写真史を歩みはじめます。第1部では写真術が渡来した日本も含め、19世紀の写真世界がどのようなものであったかを、技術の発展や写真と社会の関係を通じて探っていきます。
第1部「誕生」展示風景