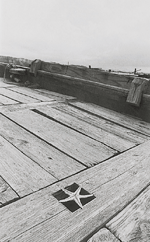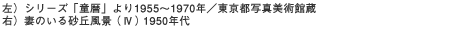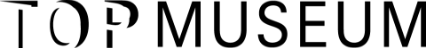学芸員コラム

「作られた夜」 1989年/鳥取県伯耆町立植田正治写真美術館蔵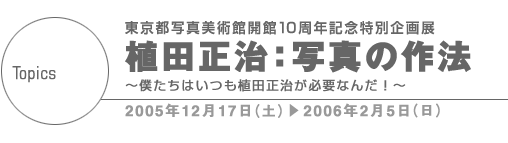
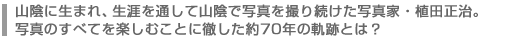
日本を代表する写真家の一人であり、当館の重点収集作家でもある植田正治は1913年に鳥取県境港で生まれました。学生時代には画家を志すも、両親から猛反対され断念。“その代わりに”と父親から貰ったカメラに没頭し、写真の楽しさに目覚めていきました。19歳の頃、地元境港に写真館を開業させた植田は、その一方で作品撮影に没頭していきます。山陰を愛し、地元の人々をモデルにした彼の作品は実に独特。広大な砂丘を舞台に被写体をオブジェのように配置するなど、斬新で遊び心とユーモアに満ちた自由で多彩な表現は「植田調(UEDA−CHO)」と称され、国際的にも高く評価されています。しかし、世界的に評価されつつも、植田は自らを「アマチュア写真家」と称しました。 “写真に対して何事にも囚われることなく常に自由な立場で撮影したい”という精神は、単に作品を残すということだけではなく、写真に関わるすべてを通じて “写真で遊ぶ”ことでもありました。彼にとって写真というのは何者にも変えがたい表現方法であり、そして人やものと対話する楽しみでもあり、それ以上に生き方そのものとも言えます。植田正治の代表的な作品に「砂丘シリーズ」や「童暦」があります。“ローカルカラー”と呼ばれたこの表現は、いわゆる報道写真的なジャーナリストの目ではなく、また純粋な芸術を求めていくアバンギャルドな芸術家の目でもなく、その地方の風土に根ざして生きていく人たちが現実をしっかり見つめていこうとする視線でした。その中で、植田は常に“写真で遊ぶ”感覚を忘れませんでした。植田は著書「私の写真作法」(2005年/阪急コミュニケーションズ)の中でこう語っています。「ファインダーというのはピントを合わせることや、瞬時に対象をとらえるための小窓としてだけでなく、自らの心の世界を展開する目として使うことができたら、また新しい世界が生まれることもあろうではないか」植田にとってファインダーとは心の窓であったのかもしれません。その心の窓を通し、あくまでも被写体に対して自然体で向き合い続けた彼の作品にはあえて正面から捉えたカメラ目線のものが数多くあります。人為的と捉えがちな撮影方法ですが、これはカメラを意識せずに撮ることが自然だと考えるリアリズム写真に対して“カメラを向けられているのに視線をそらす事のほうが不自然”という考え方の表れでもありました。つまり、写真家はカメラを持ってそこに立つという行為によって、すでに現実を変えてしまっているのです。植田はそれをしっかりと認識し、相手との関わりを通じて被写体をカメラに収めていきました。だからこそ、彼の作品からは“写真する僕”の存在が感じられるのでしょう。 

左)「裏街」1938年 東京都写真美術館蔵
右)シリーズ「童暦」より1955~1970年 東京都写真美術館蔵
1950年代、日本の写真表現に対して“絶対非演出の絶対スナップ”というスローガンを掲げ、写真界にリアリズム旋風を巻き起こした土門拳は、講演会のた めに山陰を訪れた際、「あなたの写真はとてもいい。あなたはずっとこのやり方でいくべきだ」と、植田の演出写真を認めたといいます。アプローチは違えども、写真に対する姿勢や思いは同じ。土門拳にはそれが見えていたのではないでしょうか。いつの時代にも「写真する」楽しみ方を教えてくれた植田正治。本展は没後初めての回顧展として約70年にわたる作家活動の軌跡を一望し、その表現の独自性を探ろうとするものです。約200点の作品と資料を通じて、植田の「写真」や「被写体」に対する作法を覗いてみませんか?