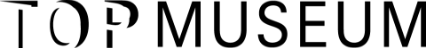学芸員コラム
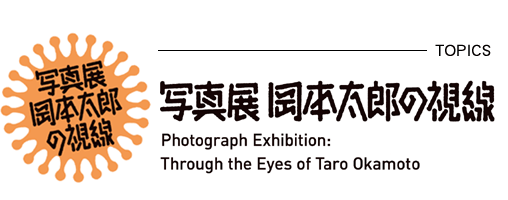



「久高のろ」(岡本太郎著『忘れられた日本〈沖縄文化 論〉』1961年刊/中央公論社)より
「那覇の街頭にて」(岡本太郎著『忘れられた日本〈沖縄文化論〉』1961年刊/中央公論社)より
「なまはげ(男鹿半島にて)」 (岡本太郎「藝術風土記・1秋田」『芸術新潮』 1957年4月号)より/図版は全て (C)財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団
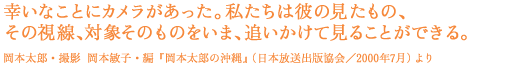
大阪万博の「太陽の塔」や「芸術は爆発だ」の言葉で知られる岡本太郎。1996年に亡くなるまでの間、彼が残した作品は彫刻、陶芸、書物など多岐に渡っており、その幅広い才能に圧巻させられるばかりです。しかし、その岡本が写真を撮影し、文章に添えて発表したり、多くのフィルムを残していたことは、最近まであまり多くの人に知られていませんでした。
岡本太郎と写真との出合いは1930年代に遡ります。当時、岡本が滞在中のパリで交流を深めていた人物にはロバー ト・キャパやブラッサイ、マン・レイなどそうそうたる名が挙げられますが、彼らから受けた影響によって、岡本はそれまで観賞用としか捉えていなかったカメラが“考えていることを表現し、伝えるツール”であるということに気づかされたというのは考えすぎでしょうか。
その後、帰国した岡本はしばらくの間、日本文化に対してやりきれない嫌悪感を抱えつつ生活をしていました。ところが、偶然訪れた東京国立博物館で縄文土器を見つけた瞬間、彼の体に電撃が走りました。生命の息吹、人間性の根源にすっかり魅せられた岡本は、東京大学の研究室で写真におさめたのです。「縄文土器論」は1952年の「みづゑ」に発表され、一大センセーションを起こします。 実はこの時、編集部では岡本の写真ではなく、プロの写真家に撮影を依頼したといいます。しかし、それは全体のトーンがきれいでバランスの取れた、いわゆる美術品をより美しく見せる写真。彼が伝えたかったのは、研究室であの日覚えた感動です。生の視線を伝えたかったのでしょう。単行本『日本の伝統』(1958年/新潮社)に収められた時、自らの写真を使っています。
「土地々々を廻り、實際に即して、こういう可能性、問題性があるということをつかみ出し、われわれ自身につきつける。たとえどんなに惨めであり、未熟であっても、まずあるがまま捉え、そこから問題を發展させて行くことだ。いや、未熟だからこそ、チャンスなのだ。それは豊かに、ほほ笑ましく問題を投げかけて来ている。 未熟ならば、だからこそ、ほとんどそれを誇っていい。そういう人間としての誇り、自覺、つまり、生甲斐をもつて、逞しく人間が息をし、生活する場所には、どこでも第一級の藝術があり得る。」(「藝術風土記 日本の風土」『芸術新潮』(1957.11)より)この時、日本の伝統や文化を掘り下げていくツールとして岡本とカメラの関係が構築されていき、それが最初に結実したものが「日本再発見—藝術風土記」(1957年『芸術新潮』連載)でした。 秋田から始まり、長崎、京都、大阪、岩手など、日本列島の風景や風俗をルポルタージュするこの連載で、岡本は現代日本のありのままの姿に出合い、その驚きや感動を一瞬、一瞬、レンズという目で捉え、意図的ではない、偶然を大切に、しかしのめり込むようにシャッターを切りました。
「聖福寺(築地にはめこまれた鬼瓦)」
(岡本太郎「藝術風土記・2長崎」『芸術新潮』1957年5月号)より
(C)財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団
当時、取材に同行していた岡本敏子さんはこう語りました。「幸いなことにカメラがあった。私たちは彼の見たもの、その視線、対象そのものを、いま、追いかけて見ることができる」(「岡本太郎の沖縄」日本放送出版協会/2000年7月より)それまでの写真という概念に“対象を理解するため”という新たな可能性を見出した岡本太郎。玄人でも素人でもない立場であった彼の作品や発言は、写真界においても一石を投じました。
本展では岡本太郎自身が発表した写真の展覧はもちろん、フィルム(スリーブ)から当時の岡本太郎の“視線”を再現し、スピード感などを体験するほか、 彼に関わった西欧写真家の作品や戦後日本の写真にまつわる岡本の言説を通して、岡本太郎と写真の関わりを探る試みです。あなたも岡本太郎の視線を体験してみませんか?