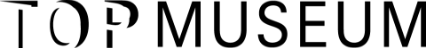作者インタビュー

与那国島、沖縄県 2004年12月 (C) 中村征夫2006

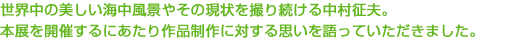
私が長い水中生活を通じて感じたことは、海の世界は謎の多い世界であり、また、地上の風景とも大変よく似ているということです。そこに水があるかないかの差で、陸地と海の風景は実によく似ています。深い海の中にも色彩豊かな「お花畑」がいたるところに展開し、造形美を誇っています。また、生物にしても不思議な生き物の宝庫です。それらは揺れ動く海中で刻々と変化し、一瞬でも同じ風景になることはありません。一方、海中は空気のない世界。水圧の壁もあり、われわれ人間が魚のように潜ったりあがったりすれば、すぐに潜水病になってしまう。空気ボンベを背負い、限られた時間の中で潜っていると「海中は人間の生きる世界ではない、人間はけっして魚にはなりきれないのだ」と実感させられます。自分の排気音しか耳に入らない世界では、自分だけが地球から飛び出して、宇宙を遊泳しながら孤独な旅を続けている錯覚におちいることもありますね。
 |
メガネモチノウオ(通称・ナポレオン)、 紅海、エジプト 1995年 ©中村征夫 2006 |
水中写真を撮り始めて40年が経ちましたが、最初のころは圧倒的な海のパワーに押されてしまい、何をどう撮ってよいのか、風景のどの部分を切り取ってよいのかと、構図すら定まらないものでした。その後、年月の流れの中で経験を積み、自分が何を写したいか、風景をどう切り取るかが分かってきましたが、それとともに海の力が以前に比べ、弱くなって病んでいる…そのような変化を感じるようになってきました。日本の海は多様性に富み、四季折々の美しい景色を海中に見せてくれます。知床の流氷から沖縄の珊瑚礁まで、地域によって全く違う顔を持っています。その海の力が弱くなってきたのです。長い年月をかけて見続けるうちに、海の姿に異変を感じるようにもなりました。藻場や珊瑚礁や干潟が減り、“これがあの美しかった海か”という現実にも立ち会わなくてはなりません。これらの現象が人間の環境破壊に起因しているのは明白ですが、そうだとすれば、ただ美しい海の風景だけではなく、その変化に目を向け、映像として記録してゆかなくてはいけないのではないでしょうか。人間はさまざまなモノを開発し、ここまで海の環境を壊してきました。けれど、それを元に戻すのも、また、人間の使命だと思うのです。今回の写真展では、ただ神秘的で美しい海の写真だけではなく、現実の海の姿もきちんと伝えたいのです。悲観するばかりではなく、展覧会をご覧になった多くの人たちが夢や希望をもってもらえるような機会になればと思っています。
(インタビュー/関次和子、東京都写真美術館)
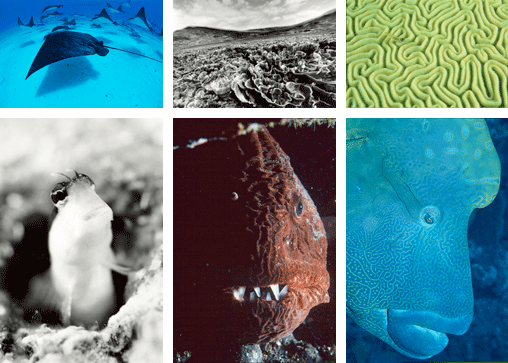
【上】
マダラトビエイ、サイパン 2005年4月 ©中村征夫 2006
ウスコモンサンゴ、白保、沖縄県、1994年1月
ノウサンゴとハゼの仲間、カリブ海、ベリーズ、2001年8月
【下】
ヒトスジギンポ、ケラマ諸島、沖縄県、1994年4月
オホーツク海の神、オオカミウオ、羅臼、北海道、1994年6月
メガネモチノウオ、紅海、エジプト、1990年