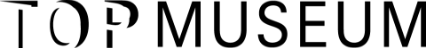作者インタビュー


mother's #52 2003年
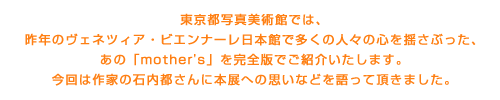 |
| もう1年前のことになりますが、 昨年の6~11月に個展を開催したヴェネツィア・ビエンナーレでの経験は、 私にとって非常に大きな収穫でもありました。 世界各国から数多くの作品が集まるヴェネツィア・ビエンナーレでは、 ひとつのパビリオン内での鑑賞者の滞在時間が短いといわれています。 そのなかで、私の写真の前で足を止めてくださる方々が多かったことには 正直いって驚きました。 なかには涙を流してじっと作品を見つめている方もいらっしゃいましたね。 個人的な問題から出発した「mother's」というテーマですが、 こうしてみると母と娘の関係というのは世界中で抱えている普遍的な問題のようです。 ヴェネツィア・ビエンナーレでは、そんなことも改めて実感させられました。  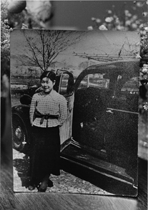 【左】02 mother's #19 2001年 【右】 03 mother's #3 2000年 |
| そもそも、私が「mother's」の原点ともいえる母の皮膚を撮り始めたのは6年前。 母が84歳を迎えた日でもありました。 その頃、岡本太郎美術館で震災にまつわる作品を発表することになったため、 関東大震災、阪神淡路大震災をキーワードに、 どちらも世代的に経験している母の火傷の痕を撮り始めたんです。 ところがその後、半年も経たない間に母は入院、余命2ヵ月と宣告されました。 その時に撮った写真が皮膚と手や足です。 12月の半ばに母が亡くなり、 とりあえず年賀状の欠礼をご案内させていただかなくては・・・と、 母の写真をハガキにプリントして送りました。「mother's」の冒頭にある、 アメリカ製大型車の横で微笑む若かりし頃の母の写真です。 そうしたら、森山大道さんからすぐにお返事が届いて、 その写真の解説が細部にわたって書かれていたんですよ。 100枚もプリントしたのに、私はそこまで写真を見ていなかった。 それは同時に母のことを知らなかったということにも値するんじゃないかと思いました。 それに加え、母が残していった生々しい遺品のやり場にも戸惑いを感じていました。 タンスを開 ければ母が着ていたシュミーズやガードルがたくさん出てくる。 口紅、鬘など直接、母が肌にまとったもので、肉体はもうどこにもないけ れど、 それを着た母の皮膚はいっぱい詰まっているんです。人にあげるには粗末なものだし、 私が着るわけにもいかない。でも、捨てることはできない。 悩んだ末、写真を撮っておけば、 捨てられるかもしれないと思って遺品に向き合い始めたんです。 遺品を撮影するというのは、ある種、対話みたいなもの。 でも、当然ながら対話をしたくても相手は喋ってはくれませんから、 “きっと、母だったらこんなふうに答えるかな”と、イメージしながら撮っていきました。  mother's #54 2002年 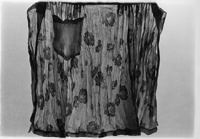 05 mother's #48 2002年 撮影は条件が揃っていたのがキッチンだったのでそこを撮影場所に選びましたが、 いま考えてみれば、そこは母がいた場所だったのです。 今回の展覧会では、ヴェネツィアで発表できなかった写真作品3点と新作の映像作品を含め、 「mother's」完全版としてご紹介しようと思っています。 母の遺品から出発し た作品ですが、ヴェネツィア・ビエンナーレなどの展示を経て、 作品自体がどんどん私の手を離れていって、いまでは自立してきていると感じています。 今回はヴェネツィアから戻ってきて初の個展ということもあり、 私自身の客観性も含めてどんなものを発見できるかが非常に楽しみでもあります。 私の展示の特徴は、写真の枚数が少なめで作品のサイズもまちまちなんですね。 ですから、観客の方々には作品に近寄ってみたり、離れてみたりと、 作 品と自分の間の空間の変化も感じながら観ていただきたいです。 やはり、写真というのは空間にすごく左右されるものですから、 そこを大切にしたいと思っています。ですから、 いまも居間やトイレに展示室の平面図を貼ってプランを考えていますよ(笑)。 皆さんがこれまでご覧になられたことのないような空間を作ろうと思っています。 東京都写真美術館の展示室には大きな柱が2本ありますから、 そこをうまく利用したいと思っていますのでお楽しみに。 そして、展覧会を作り上げるのは美術館と作家だけではなく、 見ていただく方々にも大きな役割があります。 たくさんの人々に私の作品から何かを感じ取ってもらえれば嬉しいですね。 |