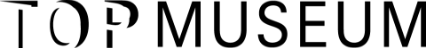作者インタビュー

 |
01「おとこと女」作品15 1961年
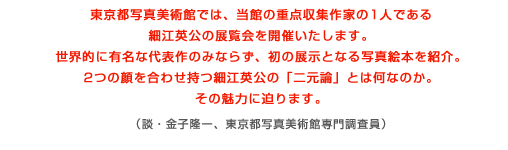
細江英公は、1950年代の末から活躍をはじめた写真家です。
ちょうど戦後から始まったリアリズム写真運動が行き詰まった頃で、高度経済成長期の中、
新たな表現が求められた時代でした。細江は、東松照明、奈良原一高、
川田喜久治などと共に、『VIVO』の活動を経て、
60年代の写真表現を切り開いた重要な写真家のひとりとして、その名を広めました。
最初に評価を受けたのは、暗黒舞踏家の土方をモデルにした「おとこと女」でしょう。
それまで“美”や“エロス”として扱われたヌードを、
直接的な“性”として真正面からとらえ、
人間の本質的な問題として物語っていったのです。
まさにそれはいままでにない表現でした。
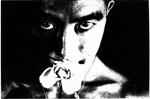 |
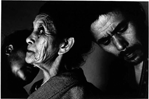 |
【左】「薔薇刑」 作品32 1961年
【右】「鎌鼬」 作品32 1965年
'63年に三島由紀夫をモデルにした写真集『薔薇刑』 はあまりにも有名です。
当時、絶頂期にある三島由紀夫を、細江は、まるでオブジェを扱うかのごとく、
ゴムホースを巻いたり、 あちこちに転がし、裸にし、時には女性と絡ませる…
そんなスキャンダリスティックな手法を用いて撮影しています。
しかし、そこには細江英公と三島由紀夫の出会いがありました。
バロック的美学を超現実的に描いた「薔薇刑」は、
まさに二人の芸術家の特異な才能が紡ぎだした成果ともいえると思います。
その後、 '69年には、日本各地の土俗的な世界につむじ風を巻き起こすかのごとく
現れる土方を神話的に表現した「鎌鼬(かまいたち)」 を、
'71年には肉体のフォルムを追及した「抱擁」を発表。これらの作品はそれぞれ、
幻想的で主観的な虚構の世界を全面に押し出しています。
そしてそれは、決して美しく煌びやかなものではなく、
もっと人間のドロドロとした存在をイメージ化していくようなものでした。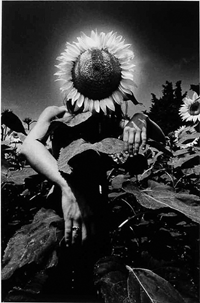
「ひまわりの子」 1992年
前衛的でグロテスクな表現者…そんな一面ばかりがクローズアップされる細江英公ですが、
実はナイーブで、ロマンチストとしての一面を持っている作家でもある、
と私は思っています。 彼が高校生時代に撮影したデビュー作
「ポーディちゃん」という少女の写真は、まさにそうした一面が垣間見られます。
日本の原風景を求めていく細江英公の軌跡には、
それに平行して西洋のモダニズムに憧れるナイーブな戦後世代の青年という、
もうひとつの細江英公の世界があるのです。
今回は、これまでの展覧会で1度も取上げられたことのなかった、
写真絵本『たかちゃんとぼく』(表紙)『おかあさんのばか』の2冊を展示し、
細江英公の新たな一面を知ろうというところが目的です。
初の展示となる写真絵本はどちらも「薔薇刑」と同じ60年代に
英語版として出版されました。つまり、「薔薇刑」と、「たかちゃんとぼく」は、
振り子の端と端であって、 その両方を行ったり来たりしているのが
細江英公という写真家なのです。それを知った上で、改めて細江作品を見てみると、
写真絵本にも人間 のやりきれない部分が出ていますし、
「薔薇刑」や「鎌鼬」のなかにも非常にナイーブな部分が見えてきます。
例えば、「おとこと女」では、ハードな作品ばかりが取上げられやすいのですが、
最後は胸板の厚い男性が胸に小鳥をそっと抱いている写真で頁を終わらせているんですね。
私はこれこそが細江英公なんだと思います。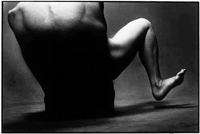
「抱擁」 作品17 1969年
かつて、三島由紀夫が婦人雑誌「マドモアゼル」に寄せた文章に、こんな言葉があります。
≪現代におけるリリシズム(抒情詩的)がどんな形をとらねばならぬか、ということが、
現代芸術の一番おもしろい課題だと私は考えている。リリシズムは、現代において、
否定された形、ねぢまげられた形、逆説的な形、敗北し流刑に処された形、
鼻つまみの形、…それらさまざまのネガティブな形をとらざるをえず、
そこから逆に清冽な噴泉を投射する。(中略)細江英公氏の作品が私に強く訴えるのは、
氏がこのように「現代の抒情」を深く潜ませた作品を作るからである。
そこには極度に人工的な創作意識と、優しい傷つきやすい魂とが、
いつも相争ってゐる≫東京では5年ぶりとなる細江英公の個展ですが、
この三島由紀夫の言葉にあるように、細江英公という写真家を重層的に
理解して頂ければと思っています。そして、これまで中心的に見えていた世界だけでなく、
別のものも見えてくるという展示構成を作りあげることで、
細江作品の抒情的でロマンティックな両面を楽しんでいただけると思います。