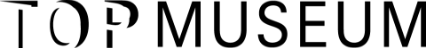学芸員コラム
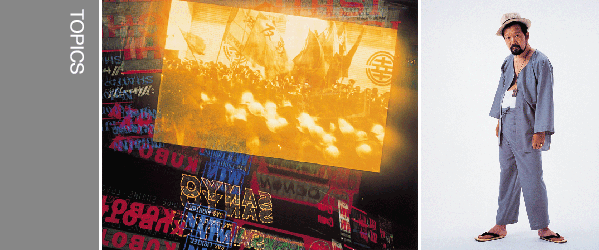
「反戦1」 東京 1968年
「写真家4東松照明」東京 1978年


名古屋で生まれ育った東松は、1954年に愛知大学を卒業した後、上京し、岩波写真文庫のスタッフに加わりました。しかし1955年に退社、翌年からはフリーランスの写真家として活躍を始めます。1957年、写真批評家福島辰夫が企画する「10人の眼」展に参加し、戦後世代の若手写真家として注目を集めます。1959年になると、川田喜久治、細江英公、奈良原一高、佐藤明、丹野章と作った写真家によるセルフエージェンシー「VIVO」に参加。この時代の代表的な作品としても名高いのが、「<11時02分>NAGASAKI」です。この作品のユニークなところは、なんといっても単に原爆の長崎をとらえたものではなく、江戸時代から続く長崎、都市としての長崎、そして原爆の長崎という複数の時間を重層的に表現したところでしょう。
その後、高度経済成長のなかで様変わりしていく都市を問題とした「I am a King」や「新宿」、基地の風景を写しだした「占領」(現在は「チューインガムとチョコレート」)など、意欲的に作品を発表し続けました。そんな東松の興味を大きくシフトさせたのが、1969年に訪問した沖縄でした。戦後社会を色濃く映し出す土地という予想に反した現地の日本古来の習俗や宗教儀礼、自然 などに強く興味を抱いた彼は、沖縄に移住し、そこでの暮らしを拠点としながら写真を撮るようになったのです。このときから彼の写真を撮る意味が大きく変わりはじめました。つまり、ただ単に何かを表現するというのではなく、自分自身の全人格、全存在、生きることそのもののメディアとして沖縄という場と写真を関わらせていったのだと思います。同時にこの沖縄での撮影を境にして、モノクロからカラーへの転換もしています。東松にとって、この沖縄という土地は、写真を撮ることの原点を示す大きな経験を可能とした場所でした。

「オリンピック・カプリッチオ」 東京 1962年
その後、いったん東京に戻った彼は、森山大道、荒木経惟らとワークショップ写真学校などの活動を展開し、若い世代の写真家たちに強い衝撃を与えました。しかし、この頃、東松は大病を患い、九死に一生を得る経験をします。そして、それを機に、療養のため、千葉県上総一ノ宮に居住を移しました。そして、この千 葉での生活を通じ、写真を撮るということにおいてもリハビリテーションが行われていったといってよいのではないかと思います。この時期の作品が、海岸に打ち上げられた漂泊物を真上からとらえた「プラスチックス」です。黒々とした砂浜に、まるで星座のように埋まった色とりどりのプラスチックは、まさに80年 代を象徴していました。そして現在、東松は長崎に拠点を移し、活動を続けています。
今回の「Tokyo曼陀羅」は、このように撮影拠点を移しながらも各地をめぐり、個別のテーマ性や時代を解体して再構築する東松照明の“曼陀羅シリーズ” の最後に位置するものです。撮影拠点とする場所はあくまでもキーワードにすぎず、例えば東京を拠点としていた時期に撮影した「恐山」などのシリーズも入っています。
東松照明の作品は、非常に現実性を重視しているため、ときにには鋭利な刃物で切られるような痛みを伴います。現在、携帯電話などで撮影される可愛い画像の対極にあるといってもいいでしょう。ですから、安易な美しさを求めたときには裏切られると思います。それほど重く、厳しい表現で私たちに問題を投げかける 作品なのです。どんなに抽象的に見えたとしても、よく見れば、それが日常的で極めて現実的なものの集積でしかないと分かります。それは、静止した写真というものでしか表現できなかったものなのです。それを最大限実現してくれるのが東松の魅力なのでしょう。

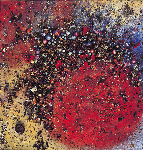
「チューインガムとチョコレート」 北海道・千歳 1959年
「ゴールデン・マッシュルーム3」 1990-91年