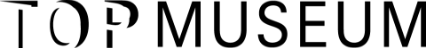学芸員コラム
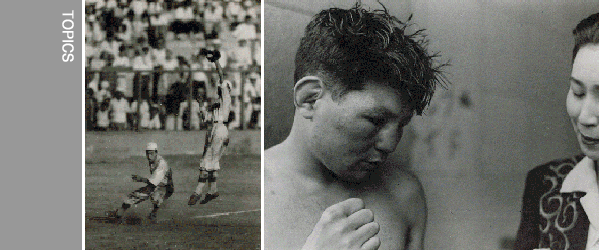
大束元 第29回全国中等学校野球大会(甲子園) 1947年
大束元 ピストン堀口 1947年
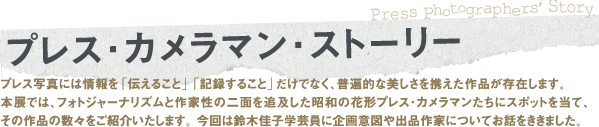
「プレス・カメラマン・ストーリー」展に登場する写真家は1930年代から1970年代前半に朝日新聞社の写真部または出版写真部に在籍したスタッフ・カメラマンです。彼らは新聞以外にも幅広い出版物で活躍していたため、すでに写真界では認められていましたが、彼らが新聞社の出身であるという事実が、私は長い間、気になっていました。
なぜかと言うと私自身、初めての就職先が新聞社でしたから、そこでのカメラマンの仕事がどのようなものか少なからず想像がつくからです。日々苛酷な任務に追われ、事件が起これば休みだろうが夜中だろうが関係なく駆けつけ、撮影対象も事件・災害・政治・スポーツ・エンターテイメントなど多岐に渡り、ポートレイトやランドスケープ、スティル・ライフ(物撮り)、舞台写真など、プロフェッショナルとしてあらゆる種類のニーズに対応するテクニックや行動力を備えていなければ務まらないのです。自分の表現を突き詰めようなどと考えようものなら「何をねぼけたことを」と一喝され、情報をいち早く「伝える」「記録する」という目的のために全能力を捧げ、個性を押し殺す。これこそが新聞社のカメラマンの生きる道であると思っていました。ですから、影山光洋や大束元、吉岡専造、船山克、秋元啓一のような新聞社のカメラマンでありながら、フリーのような異彩を放つ存在に関心を持ったのです。 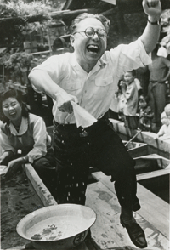
大束元 石黒敬七 後ろは松田トシ(歌手) 1948年
新聞社が写真部をつくりカメラマンを独立した組織体制にしたのは、昭和の初めで、朝日は他社に先駆け、昭和3(1927)年でした。それ以前は写真製版会社にカメラマンがいて、新聞社はそこからにニュース写真を買っていたので、製版までしてもらえるという便利さがあったのです。しかし、各新聞社の競争が激化するにつれスピードが重要になると、自社で製版設備を持ち、優秀なカメラマンを採用するようになりました。最初は写真製版部や社会部、編集部などにカメラマンは所属し、製版や記者を兼ねることもあったようですが、次第に写真取材だけを専門にする写真部が朝日を皮切りに各社、次々に体制を整えて行きました。
このような当時の状況のなかで、影山氏は昭和2(1927)年に朝日に入社しますが、朝日が学校で写真を学んだ本格的なカメラマンを採用する初めてのケー スだったそうです。この時期から日本の新聞社におけるカメラマンの存在は活気づいていきます。世界的に見ても1930年代から70年代前半という時代は、ちょうど『ライフ』誌の36年の創刊と72年の廃刊という出来事を間にはさみますので、ロバート・キャパやユージン・スミスに代表されるカメラマン全盛期に重なるのです。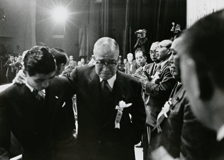

吉岡専造 鳩山退場 1956年 「現代の感情」より
影山光洋 小麦の収穫祝い、家族の肖像 「芋っ子ヨッチャンの一生」より 1946年
新聞社が週刊誌などのグラフ雑誌に力を入れるにつれ、写真部だけでは用が足らず、出版写真部という組織が現れます。その出版写真部での、大束氏の活動は目覚ましいものがあります。大束氏はアート・ディレクター的な感性を持ち合わせたカメラマンで吉岡氏や、船山氏とともに、朝日の三羽烏と称され、『アサヒカメラ』に「新東京シリーズ」や「現代の感情」などのシリーズを中心的に手がけ、優れた作品を発表しています。大束氏が先導して行ったことは新聞社の写真が持つ「無名性」のようなものに対する挑戦だったといえるかもしれません。
大束氏が自分の表現にこだわった「作家性」について考えるとき、この「無名性」ということばが浮かび上がってきます。新聞をはじめプレスの写真は誰の撮影かは問題にされず、写されている被写体そのものに、注意が向けられることが一般的です。そのことは写真が持つ宿命であり、ここに、写真の原点に立つ重要な鍵があると考えます。本展では、カメラマンたちの際立った活躍に焦点を当てると同時に、新聞社の構造や新聞をはじめとするプレス写真の根源的な使命を明らかにすることによって、表現とは何かという普遍的な問いへの回答を考える場にできればと思っています。
(インタビュー 2009年2月)