プレス・カメラマン・ストーリー
2009.5.16(土)—7.5(日)
- 開催期間:2009年5月16日(土)~7月5日(日)
- 休館日:毎週月曜日(休館日が祝日・振替休日の場合はその翌日)
-
料金:一般 500(400)円/学生 400(320)円/中高生・65歳以上 250(200)円

- ※各種カード割引あり
( )は20名以上団体、当館の映画鑑賞券ご提示者、上記カード会員割引(トワイライトカードは除く)/
小学生以下および障害者手帳をお持ちの方とその介護者は無料/第3水曜日は65歳以上無料
ジャーナリストでもあり、アーティストでもあった。花形プレス・カメラマンたちの、自由な表現に秘められたストーリー!
さまざまなプレス写真が氾濫し報道されていく現代、ふと1枚のプレス写真に大きく心を打たれることがあります。何気ない日常の風景、誰も足を踏み入れていない地でのスクープ、時代を象徴する決定的瞬間など、情報を「伝えること」「記録すること」を超えて、普遍的な美を携えた写真は私たちの心をとらえて離しません。
この展覧会では、昭和の戦前・戦中・戦後の一時期に、作家性を強く意識した5人のプレス・カメラマンを中心に焦点をあてます。朝日新聞社を支え、花形プレス・カメラマンとして活躍した影山光洋・大束元・吉岡専造・船山克・秋元啓一をはじめとする写真家たち。彼らは自社の仕事のみならず、他社の雑誌にも作家性を強く打ち出した作品を発表し、フリーの写真家たちと同じように自由な創作活動を行いました。<新聞社に所属したスタッフ・カメラマン>という枠を越えて活躍できたという状況は非常に特殊で、彼らが朝日新聞と関わった時期がもっとも顕著であったといえるでしょう。
本展は、プレス写真の使命とは何なのかを考察しながら、彼らがどのようなシステムを背景に仕事をしたのか、自由な環境が豊かな表現を生み出すことができたのか、という問いかけをベースに検証します。プレス・カメラマンの仕事を「フォトジャーナリズム」と「作家性」の観点から紹介し、平成20年度に新たにコレクションに加わった影山・大束の当館初公開作品も含め、収蔵作品を中心に幅広く展覧します。
■影山光洋(かげやま・こうよう 1907-1981)
1907(明治40)年静岡県浜松市に生まれる。浜松商業を卒業後、親戚が経営する写真修整業の画光舎に勤める一方、1927年東京高等工芸学校の一期生として入学する。東京の街を撮影した卒業制作「東京百景」が朝日新聞社の写真部長に認められ、1930年、同新聞社の写真部に配属され、新卒でカメラマンとして採用される。1934年、東北地方の大凶作。1936年、隠しカメラで撮影したニ・ニ六事件。日華事変勃発後、1937年、従軍カメラマンとして中国に滞在、南京陥落。1938年、徐州作戦等に従軍。など、時代の重要な出来事を記録した。また、1942年にはシンガポール陥落に際し山下・パーシバル会談の「イエスかノーか」の場面を撮影、大スクープとなった。1945年、太平洋戦争終結後、朝日新聞社を退社するが、翌年、朝日新聞社協力により創刊した『函館新聞』の写真部長に就任、軌道に乗るのを見届けフリーになる。独立後、1946年から1951年までの短い時間を生きた愛児賀彦の一生を綴ったアルバム「芋っ子ヨッチャンの一生」(1951年、新潮社フォトミュゼより刊行)を制作。見事な家族像を描写している。また、1948年の沢田美喜との出会いから「エリザベス・サンダース・ホーム」の混血児たちの成長過程をライフワークとして記録する。1960年には母親の生前40年間の記録を「おふくろ」写真展として発表。生涯を通して、写真の記録性にこだわった。
■ 大束元(おおつか・げん 1912-2002)
1912(明治45)年5月10日、東京都北区多滝野川で生まれる。父は写真修正の先駆者、大束昌可。29(昭和4)年、東京府立第5中学校を卒業、父のすすめで東京高等工芸学校(現・千葉大学)写真科に進学。在学中から『光画』の例会に父とともに顔を出し、33年には作品を『光画』に発表。34年、銀座の紀伊國屋画廊で商業写真展と銘打った初個展を開催。銀座商業写真研究所をつくり、スタジオ撮影などを行う。同年秋、朝日新聞大阪本社に社会部員として入社。37年より中国大陸を中心に取材・撮影し、新聞紙上で「写真と文」をひとりで担当するスタイルを確立する。48年、出版写真部へ移り、舞台写真やポートレイトを撮影。50年から『アサヒカメラ』を舞台に《新東京風景》シリーズなど都市やそこに住む人を捉えた作品を発表。58年、出版写真部長になる。63年、全日本写真連盟事務局長に就任。64年、「オリンピック東京大会芸術展 日本・カラー1964」(東京銀座・松屋)に出品。66年「マグナム・フォトス 地上に平和を」展(東京銀座・松屋他巡回)、「H. カルティエ=ブレッソン 決定的瞬間その後」展(東京・京王百貨店)などの企画を担当。朝日新聞社を退職後、全日本写真連盟理事を務め、アマチュア写真の発展に尽力する。89(平成1)年、回顧展「大束元の軌跡」(東京・コニカプラザ他全国巡回)が開催された。
■吉岡専造(よしおか・せんぞう 1916−2005)
1916(大正5)年12月15日、東京に生まれる。39(昭和14)年東京高等工芸学校(現・千葉大学)写真部を卒業し、東京朝日新聞社に入社し、編集局写真部を経て出版局写真部に勤務。40-41年に従軍し、42年からは海軍報道班員として戦場や周辺地の取材をする。高度経済成長期の日本社会を政治から一般大衆文化まで、広い視野の切り口で撮り続け、『アサヒカメラ』で複数写真家による連載シリーズ「現代の感情」等に発表。57年3月号掲載の《鳩山退場》は、引退を表明した鳩山首相を画面中央で捉えながらも、次期政権を争う政治家たちにピントを合わせた作品で、作家の瞬時の判断と技量がうかがえる。この作品により、同年、第3回毎日写真賞特別賞を受賞。他の代表作として、実子の誕生から1年1日も欠かさず撮り続けた写真を妻のメモと共に綴った『人間零歳』を60年に刊行。67年には、写真嫌いの異名をとる政治家に密着した写真集『吉田茂』を刊行。71年、朝日新聞社を退社し、フリーランスとなる。同年、宮内庁の委嘱で昭和天皇の御影を撮影したことを契機に、72年から7年間にわたり撮りためた吹き上げ御所内の植物を、80年、写真集『吹上の自然』にまとめた。
■船山克(ふなやま・かつ 1923− )
1923年(大正12)年2月1日、兵庫県武庫郡精道村大字芦屋に生まれる。40年、慶応大学予科に進学し、カメラクラブに参加、野島康三らから指導を受ける。早慶展や 六大学写真展に出品した関係から早稲田大学の秋山庄太郎や稲村隆正らと親交を持つ。43年、学徒出陣で横須賀の武山海兵団に入団し、翌年、フィリピン・レイテ湾に突入する艦隊を援護するため出撃する。その際、ライカaで撮影する。45年、朝日新聞東京本社に入社。新設された出版写真部のスタッフ・カメラマンとして配属され、『アサヒグラフ』を中心に活躍。筋金入りの根性を持って、危険な撮影に次々と挑んだ船山は数多くの武勇伝を残す。312メートルの「東洋一の鉄塔」に自ら上って撮影した写真は話題になり、「高いところの写真は船山」と言われるようになる。また、大束、吉岡とともに「朝日出版写真部の三羽烏」と言われるようになり、自主性を持ったスタッフ・カメラマンとして時代をリードする。船山の活躍で朝日の出版写真部を志望する若者が殺到する。
■ 秋元啓一(あきもと・けいいち 1930−1979)
1930(昭和5)年3月2日、埼玉県に生まれる。51年、東京工業専門学校写真工業科を卒業。52年、朝日新聞出版局出版写真部に入社し、同社のカメラマンとして、49歳の生涯を終えるまで報道の現場で活躍した。62年、高度成長期の日本に頻発し始めた公害の風景を上空から風刺的なアプローチで捉えた、『週刊朝日』の企画「ニッポン風船旅行」を連載。64年から開高健とともに度々ベトナムに赴いてベトナム戦争を取材し、翌年にかけて『週刊朝日』に「ベトナム戦記」として連載される。このルポルタージュ写真は彼の代表作のひとつで、中でも、65年1月29日未明サイゴンで行われたベトコンとみなされた少年の公開銃殺刑の一連の写真は南ベトナム側の負の側面を捉えた貴重な記録とされている。開高とのコンビは『週刊朝日』を舞台にその後も続き、ビアフラ戦争、中東戦争を共に取材している。また、71年に刊行された開高の旅と釣りのエッセイ集『フィッシュ・オン』に収録された写真は、紀行写真家としての優れた側面を表している。それ以外にも新聞社のカメラマンとして事件、風俗、紀行など幅広い分野で記録を行った。77年出版社写真部長になるが、ガンを患い、惜しくも79年6月27日に死去。


影山光洋 さつま芋を肩に 「芋っ子ヨッチャンの一生」より 1948年11月
秋元啓一 「銃殺ーある高校生の死」より 1965年
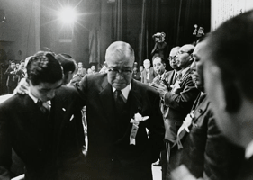
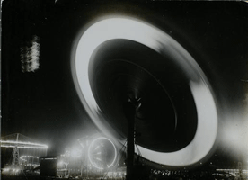
吉岡専造 鳩山退場 「現代の感情」より 1956年
船山克 後楽園夜景 1950年代
□主催:東京都 東京都写真美術館/朝日新聞社
□後援:日本新聞博物館
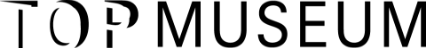


![チラシ2[pdf]](http://topmuseum.jp/upload/3/198/thums/2009_010_b.png)
![出品作品リスト1[pdf]](http://topmuseum.jp/upload/3/198/thums/press02.png)
