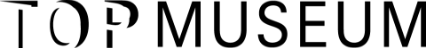作者インタビュー

ベニス、1985
東ベルリン、1985
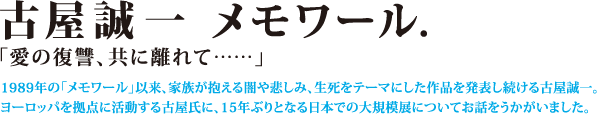
ーメモワールのシリーズを撮り始めたきっかけを教えてください。
多くの写真家や写真を使って表現を志す人たちは、まず何を撮りたいのか、表現したいのかなどとテーマを決めてから撮影を始めますが、僕の場合は少し違っていると思います。1989年以来「メモワール」というタイトルの個展や作品集を発表し続けてきて、この春、多分その最後となる5冊目の写真集を出版します。つまりメモワールという言葉が内に含みもつ世界が僕のこれまでの写真表現の原点にあったのは確かですが、このタイトルが先にあったのではないということです。1985年に妻の自死という「事件」を体験してから4年後、初めて個展という形で写真を発表する機会を得たときに色々と思案したあげく最終的に「メモワール」という言葉に辿りつきました。
今振り返ってみると、時の経過とともにその「事実」と正面から向き合わなければならない状況に追いこまれたのだと思います。僕がもう一人の僕、自己を相手に問答を始めるために手元に残った写真やその他の記録をまず見ることから始めました。それから25年、時間と空間を超えて生きのびつづける記憶を、その度ごとに「現在」へと呼び戻しては蘇生させ編み直してきたわけですが、回を重ねていくうちにいつしかシリーズという言葉が使われるようになりました。まず写真や経験などが先に在ったということで、シリーズやタイトルのために写真が撮られたということではありません。
ー今回の「メモワール.」展は、これまでの「メモワール」の中でどのような位置づけとなるのでしょうか。
今回の展覧会は東京都写真美術館が内容的にも時間的にも僕の制作活動のほぼ全域から選択、収集した作品から構成されています。これまで20年間余り多かれ少なかれ「メモワール」という主題をとりまく形で作品発表をしてきましたが、こうしてほぼ全域に渡った作品をもとに大きな個展を開催するのは95年以降初めてのことです。自分以外の人にその展示構成を任せたという意味でも、僕にとって全く新しい試みとなりました。それと同時に、この展覧会が最後のメモワール展になる、ピリオドが打たれたということです。彼女の死後、無秩序な記憶と記録が交錯するさまざまな時間と空間を行きつ戻りつしながら探し求めていたはずの何かが、今見つかったからというのではなく、おぼろげながらも所詮何も見つかりはしないのだという答えが見つかったのではないかと。しかしピリオドには終止符という意味とともに期間や時限の一区切りという意味もありますので、この先どのような展開をしていくのか本人にも不確かなことです。
ー展示は7つのゾーン(「光明」「円環」「境界」「グラビテーション」「クリスティーネ」「エピファニー」「記憶の復讐」)で構成されています。
基本的に写真展の展示、空間構成などはグループ展、個展にかかわらず可能な限り僕自身が決めるのですが、今回の展覧会では展示コンセプト全てを東京都写真美術館の学芸員である石田留美子氏と巡回先の熊本市現代美術館の冨澤治子氏に託しました。この7つのゾーンもお二人の考えのもとに生まれたもので、カタログに掲載されるそれぞれの論文で何らかの言及がなされるものと想像しています。
あえて言えることは、もし僕が一人でコンセプトを考えることになっていたのなら、決してこのようなゾーンによる仕分けにはならなかった、なり得なかったということです。つまり、僕には思いもよらなかった展示構成であり、それゆえに僕が長い時間をかけて模索しつづけてきたらしい何かがあぶり絵のごとく浮かびあがってくるのではないかという期待感を抱いています。数珠の珠(たま)をつなぎとめている糸、外からは見えないゾーンの芯を流れているようなものが見えてくるのではという予感と言えるかもしれません。
ー長くヨーロッパで生活されていることは、写真に対する考え方に影響を与えているのでしょうか。
23歳で横浜港を発ってから37年間ほぼオーストリアに住んでいますが、その事実が「写真に対する考え方」にどのような影響を与えたのか、答えに困ってしまいます。その間日本に住んでいないわけですから比較のしようがないというか。ただ、外国に住むということは言葉の壁や生活環境の違いなどに始終さらされながら生きることですから、ある種の緊張感や孤独感から免れない環境にいるということです。20歳過ぎまでに日本で会得したものや性格などはいかに長く外国に住んでも消え去るものではないし、二つの世界を行ったり来たりしているような不安定な不確かな感覚から逃れられない。絶えずアンテナを張っているような感じとでも言えるかと思います。この感覚がきっと僕の写真に何らかの影響を与えているかもしれませんが、その判断は他者に委ねるしかありません。
いつか何処かで発表するとか、人に見せるという目的で写真を撮っているのではなく、日常生活の中で一瞬ひらめきを感じるような場面に出会った時に「ただ」撮るというのが僕の基本的な写真との関わり方です。いわゆる劇的な場面とか、美的構図を追い求めるようなものではなく、カメラをもっている誰もがきっとするように日常の出会いを記録しているようなものですから、これからどのような写真を撮っていきたいとか考えたことがありません。ただ、時代や俗界の風潮に迎合しそうなコンセプトをまずつくって、それに合った図柄の採集に出かけてみようかと時々考えたりしますが、いざとなったらその行為のばかばかしさをもう一人の僕から笑い飛ばされるに違いありません。受動性が支配する世界、ただただ待つしかないというのが僕の写真かも知れません。
ーどのように展覧会を見てもらいたいですか。
どのように見るかは、その人の資質と感性が決めることですからこちらからそれを要求するものではありません。写真そのものは僕が撮ったものですが、一旦僕から離れた時点でそれは何処にでもあるような一枚の写真となり、ただ、今目の前に在るというだけでそれ自体何も主張しません。そこに何らかの意味を読み取り、新しい言葉を発見することは鑑賞者に委ねられます。写真は一つの言葉に触発されてさらなる言葉を発見する過程において、丁度その中間辺りに不安定な状態でぶら下がっているようなもの、新たな世界の認識への橋渡しをするメディアでもあると思います。
人は必ず負の世界を自己の内に抱えていますが、それを外に出さずに生きています。でも、哀しみや苦しみといった負の感情も人が生きていくうえで欠かすことのできない豊かさをもたらすものであるということを、この展覧会を通して感じてもらえたらと思います。写真とは心の奥深く籠る「どうしようもない何か」と向き合い、さらにそれを表現の場へと引き上げることを可能にしてくれる素晴らしいメディアであるということも。
(2010年1月 インタビュー)

ウィーン、1983
グラーツ、1992