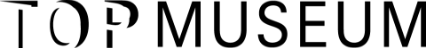学芸員コラム

木村伊兵衛「那覇の市場」 1935年



1988年から15年にわたって続けられてきた当館のコレクションには、古今東西の優れた写真作品が23,000点以上収蔵されています。その特徴として、約70%が日本人による作品であるということがあげられます。これは幕末に写真術が渡来してから今日に至るまでの日本の写真の歴史と現在を体系的にたどることができるということでもあります。それと同時に、世界の写真史を理解するために海外の美術館に対しても誇りうる写真史上重要な欧米の作品も数多く収蔵しています。今回の連続4回にわたる写真展は写真が私たちの生活や思考にどのような役割を果たし、影響を与えてきたかという切り口で、東京都写真美術館がこれまで収集してきた作品の魅力をご紹介していきます。
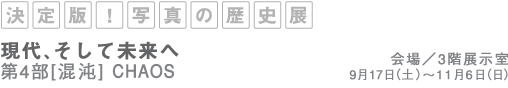
 |
◎出品作家: ルイス・ボルツ、ゲリー・ウィノグランド、ダニー・ライアン、ルーカス・サマラス、柴田敏雄、オノデラユキ、チャック・クロース、ジョエル・マイヤウィッツ、佐藤時啓、杉浦邦恵など |
現代の写真を語る上で重要なことは、表現手段や創作方法がいかに拡大され、進化しようとも、それでもやはり写真は<社会を映す鏡>であり続ける、ということでしょう。しかし、ここでいわれる<社会>とは、単にわれわれを取り巻く外側の社会を指すのではなく、むしろ、われわれが内に抱える個人的な問題を問い直す「場」としての様相を呈してきました。1977年、ニューヨーク近代美術館で開催された写真展「鏡と窓」は、そのことを考える上で象徴的なものといえるでしょう。外部世界の現実の記録をとらえた窓派と、写真家自身に内在する視覚表現をあらわす鏡派というふたつの観点の表示は、その後の写真評論において大きな問題提起を投げかけるとともに、一方で写真家とともにアーティストを交えたセレクションも話題となりました。80年代に入ると、アメリカ経済の状況にともない、写真の市場が大きくクローズアップされてきます。「ヤッピー」と呼ばれる新たな富裕層の台頭は、彼らの感性に応えるアーティストたちを積極的にサポートし、やがてその波はバブル期の日本へ、そして世界へと拡がっていきました。現代の写真文化を取り巻くさまざまな社会環境は、なかば必然的に写真家たちの生き方やわれわれの写真の見方を変えていきました。こうした写真の形態の〈多様性〉は、同時に〈混沌〉に満ちた写真の現状をも生み出したのです。開館10周年特別企画展の終章を飾る第4部「混沌」では、1970年以降から現代までの写真表現を通して、時代背景とともに変化してきた作家像と、美術館と写真の新たな関係性について考えていきます。
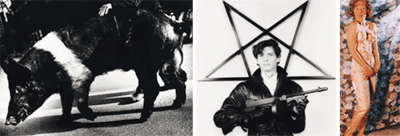
左)森山 大道 「猪豚」1975年
中)ロバート・メイプルソープ「銃を持ったセルフポートレイト」 1983年
右)シンディ・シャーマン 「アンタイトルド」 1983年