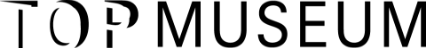作者インタビュー

なにものかへのレクイエム (記憶のパレード/1945年アメリカ) 2010年
なにものかへのレクイエム (VIETNAM WAR 1968-1991) 2006年
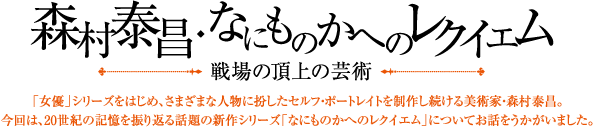
ーシリーズの全体像について教えてください。
現在私たちは21世紀を生きています。しかしこの21世紀は、かつて人々が想像していたような夢の世紀ではないようです。前の世紀である20世紀をブルドーザーで更地にして、20世紀的記憶を忘れ、その上にどんどん21世紀が出来上がってきつつあるように思います。
私はここでいったん歩みを止めて、「これでいいのか」と20世紀を振り返りたいと思いました。過去を否定し未来を作るのではなく、現在は過去をどう受け継ぎ、それを未来にどう受け渡すかという「つながり」として歴史をとらえたい。
そしてこの関心事を私は「レクイエム=鎮魂」と呼んでみたいと思いました。レクイエムとは、過ぎ去ってしまった人や時代や思想に対する敬意の表明です。しっかりとそれらを記憶に残す儀式です。「私はあなたを忘れません」ということの証としてのレクイエム。
ルネサンスがそうであったし、ゴヤもレンブラントも、みんな過去をいかにして現在に活かせるかという大胆な実験を繰り広げてきました。過去への敬意(レクイエム)なくしてすぐれた芸術は存在しないと私は断言したい。私の作品も「過去をいかに今に活かせるか。そういう過去との対話」としての、私なりのレクイエム、ととらえていただけたら嬉しいのです。
今回の展覧会は、第一章「烈火の季節」、第二章「荒ぶる神々の黄昏」、第三章「創造の劇場」、第四章「1945・戦場の頂上の旗」の4つのパートで構成されます。三章と四章はすべて新作です。映像作品と大型の写真作品で、多くはモノクロ写真の展示です。このモノクロ写真も、20世紀的世界を現代という器に移し替える方法だという思いから銀塩写真にこだわりました。
ー森村さんが考える20世紀とはどういう時代なのでしょうか?
私は20世紀社会を構成する思想的要素は、「ロシア革命」「ファシズム」「アメリカ」の3つだと解釈しています。そしてこの3つを、私は芸術家という立場からとらえたい。芸術家的立場というのは「私的世界から発して社会に至ること」だと私は思っています。「私的」だから、一般論ではありません。一般論ではないから、誰にでも同じ解答となる科学とは異なります。
しかしその私的世界が、私的に生きられた手応えとして観る人に伝われば、人は動く。「モリムラにとっての20世紀はこういうものだった。ならば私にとっての答えはなんだろう」と、人々が自問する扉を開ける装置としての作品ができたらいいなと思います。ゲバラやレーニン、ピカソなど、今回選んだ20世紀人は、そういう意味ですべて、1951年生まれの私の個人的な想い出と結びついた人々です。「私」と「彼ら」(あるいは「主」と「客」、あるいは「個」と「社会」)といった対極する両者に架け橋を渡す作業、それが私にとってのセルフポートレイトであると言ってもいいかもしれません。
ー新作の映像作品では、なぜ硫黄島のイメージをテーマにされたのでしょうか。
20世紀を巡る旅人としての「私=モリムラ」は、ロシア革命から、べトナム戦争、三島事件… と、世界と日本の様々な20世紀的事象を彷徨うわけですが、やがてその振り子が収斂する「時」として、1945年に行き着きました。それは19世紀をひきずる20世紀から、21世紀を予告する20世紀への変わり目の「時」でもあります。
第四章(終章)として、私はこの「1945」をテーマにし、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの1945(アジアは正確には1946)を作品化しています。この「1945」の歴史的イメージとして、硫黄島に星条旗を掲げる兵士達の写真もテーマにすべきだと私は考えました。日本とアメリカの出会い、戦場の意味、戦場に旗を掲げる事の意味、20世紀の前半と後半をわかつ山の頂上に立っているという感覚、しかしこれは終わりではなく、戦場の悲惨は旗が掲げられた後に起こったという教訓。いろいろな意味において、「20世紀とはなにか」という問いへの答えに至る手がかりをこのイメージがはらんでいると思えました。
ー作品の中で、森村さん扮する兵士は芸術家の道具を持ち、また自身のお父上のイメージも重ねられているようです。彼は森村さんに近い存在なのでしょうか。
かつて友人が私に言ったことがあります。「みぢかな人を救えないで、どうして人類を救えるなんて言えるのか」と。私が美術(芸術)にこだわるのも、この問いへの答えを見つけ出そうとしているからかもしれません。私は、芸術というのは勝利者のためにあるのではないと考えています。経済も政治もスポーツも、みんな基本的に勝利者優先の世界です。
消え行くものや、敗れ去るものや、弱いものや、目立たないもの、そういう一般的には社会のおちこぼれなどと呼ばれる存在を輝かせる機能は、芸術以外は持ち得ないとさえ思います。登場する兵士は名もない一兵卒(私の父もそうであったように)です。その兵隊に芸術を生み出す道具を持たせ、よろよろと山の頂上に向かわせたい。様々な20世紀の「男達」を経巡るうちに、そういう無名の兵士に至ってしまったというのは、自分でも思いがけない結果です。
ーこの作品では、戦場の頂上に芸術の旗を立てる重要なシーンがあります。
私は芸術という領域で仕事をしていますから、「芸術とはなにか」という問いはとても大切に思っています。政治的にでも社会学的にでも思想的にでもなく、芸術的感性を通してみえる20世紀像を作り出したい。ちょっとおおげさな言い方になりますが、万感の思いを込めて、「戦場の頂上に旗を立てるシーン」に挑みたい、なんて思っています。
ー以前に発表された「女優」シリーズに出てくる20世紀の女たちと、今回の20世紀の男たちはどう違うのでしょうか。
20世紀に「オンナ」はどこで輝いたのかと考えた時、私は映画の中で輝いていたと思い当たりました。では「オトコ」は? 「オトコ」は現実で輝きました。そのあまりにも現実的である現実が、戦場や革命の現場であったと思います。そして「オトコ」達は、必然的に「現実」を撮る報道写真として記録された。「オンナ」は銀幕のフィクションである。「オトコ」は報道写真というドキュメントである。この虚実の組み合わせによって20世紀は構成されていたのだと思います。
私は「オトコ」に生まれた。女優シリーズで「オンナ」に性転換(もちろん精神的に)した。そしてここに来てさらに「オトコ」に性転換した。ではこれで終わりなのか。そうではないと思います。「オトコ」と「オンナ」を巡る旅の次の行き先は? それはまた別のストーリーを待たねばならないことなので、これからのことですね。
(2009年11月 インタヴュー)


なにものかへのレクイエム (遠い夢/チェ) 2007年
なにものかへのレクイエム (夜のウラジーミル 1920.5.5-2007.3.2) 2007年