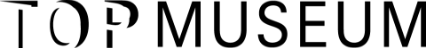トピックス

左)植田正治 後ろ向きの少女 1949年
右)ジャック・アンリ・ラルティーグ シャモニー、1918年1月8日
Photographie J H Lartigue (c)Ministère de la Culture - France / AAJHL

植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグは、日本とフランスそれぞれを代表する「偉大なるアマチュア写真家」。2010年に開催された「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ・ブレッソン 東洋と西洋のまなざし」展に続き、日仏の作家二人展の第二弾として企画されたのが本展である。アマチュアだからこそ純粋に、そして自由に制作された写真は、どれも屈託がなく、見る者の心をも幸せにする不思議な力を放っている。そんな二人の作家の魅力を展覧会企画者である、鈴木佳子、金子隆一の両学芸員にうかがった。
植田正治がラルティーグ作品の大ファンだったことが、今回の二人展が実現するきっかけになったそうですね。植田が憧れたラルティーグとはどんな写真家だったのですか?
鈴木「ラルティーグは1894年、フランスでも屈指の財閥の家系に生まれています。70歳を目前にした1963年に、ニューヨーク近代美術館で個展が開催されて初めて名が世に出るわけですが、それまで写真家としては全く知られていませんでした。繊細な性格だったようで、こどもの頃、大好きなママ、尊敬するパパ、強いお兄さん、仲の良い従兄弟たちと過ごす毎日がとても幸せで、その一瞬一瞬が失われていくことが耐えられずに、思い悩んでしまった。このままではいけないと父親がカメラを買い与えたことが、写真を始めるきっかけになったそうです。その頃から幸せな出来事を一つももらすまいと、生涯を通して日々写真を撮り、日記やアルバムにまとめていくわけです」
 |
 |
左)ジャック・アンリ・ラルティーグ
ぼくの空中プロペラ式水上滑走艇、板の上に取り付けた「ゴーモン・ブロックノート」カメラを使ってお風呂の中で撮った写真、
シャッターはママンが切った、コルタンベール通り40番地、パリ、1904年
Photographie J H Lartigue(c)Ministère de la Culture - France / AAJHL
右)ジャック・アンリ・ラルティーグ 「アンナ・ラ・プラドヴィナ」と呼ばれたアルレット・プレヴォ-、
連れている犬はシシとゴゴ、ブローニュの森の大通り、パリ、1911年
Photographie J H Lartigue(c)Ministère de la Culture - France / AAJHL
では、写真で作品を作っているという意識はなかったのですね。
鈴木「ラルティーグはインタビューでも、有名な写真家の名前をほとんど知らないと答えています。写真はあくまでも、自分の楽しみのためだけに撮っていたんですね。
その彼のアルバムを見ていくと、別荘でプールに入ったりテニスをしたり、映画スターやスポーツ選手との華やかな交流も出てきたりと、まるでおとぎ話のような人生が続きますが、他の登場人物たちと一緒に写る本人はとても静かな表情で、強烈さがない。実際には苦悩を抱えてもいたし、晩年にいたるまで落ち着いた気持ちになることが難しかったと、関係者には漏らしたこともあったそうです」
植田正治のほうがアマチュアということにより意識的だったのでしょうか。
金子「彼は、“生涯アマチュア写真家”“アマチュア精神”という言葉に非常にこだわっていました。60年代末から70年代はじめに、商業や広告、報道を目的とはせず純粋に写真表現を行う写真家を“シリアスフォトグラファー”と呼ぶ言い方が出てくるんですが、植田正治はそれに対応する考え方として“アマチュア”という言葉を頻繁に使うようになります。職業写真家ではないからこそ、自由な表現が可能なんだという意味も含まれているのかもしれません。彼はそんなふうにして、自分の写真家としての生き方を位置づけようとしたんですね」
鈴木「植田はその当時、雑誌『カメラ毎日』の山岸章二編集長と懇意にしていたそうですが、その山岸編集長のところに夜中でも電話をかけて、新しい写真について意見を聞きたいと言って、何時間でも話しをしていたそうです。
家族にだって都合はあるだろうし、こどもたちも遊びに連れて行ってほしい気持ちもあったかもしれませんが、そんなことはおかまいなしに、鳥取砂丘に連れて行っては、ポーズを撮らせて、納得のいくまで撮影を続けたわけですね」
 |
 |
左)植田正治 パパとママとコドモたち(I)1949年
右)植田正治 「風景の光景」より 1970-80年
金子「ラルティーグの写真は、いわゆる家族アルバムの写真と言えます。一方、植田正治の娘のカコさんは、うちには家族写真がないんですよとおっしゃっていた。みんな作品なんです、と。
ラルティーグと植田正治は同じアマチュアでも、写真の成り立ち方が全然違うんですね。植田正治は、そうやって写真で作品をつくることが日常でしたが、かたやラルティーグは日常が写真になっていった」
鈴木「そして、対極ではありながらも、どちらも非常に好奇心旺盛で、写真の新しい表現を追求することにはどん欲でした。
ラルティーグは、1900年前後、写真撮影で面白いのは瞬間を撮ることだと、とても早い段階で悟って、それを実現させようと様々な試みをしていくんです。技術的にはシャッタースピードが今よりもずっと長く時間がかかっていた時代です。乳母にボールを投げさせて撮った作品(「ぼくの乳母デュデュ、パリ」1904年)は、まだ少年時代のもので、これは最初期に彼が撮った、瞬間的な表現を試みた写真のひとつです。
さらにラルティーグの写真はすごくスピードが感じられるものが多い。家族で自動車レースを見に行くとか、兄が飛行機に乗ることを趣味としていたこともあって、ラルティーグはそれらを撮ることに熱中して、独自にテクニックを身につけていきました。写真史を知らないと言いながらも、写真の動向を先取りして、優れた作品を数多く制作しているんです」
 |
ジャック・アンリ・ラルティーグ
ビビとマミー、オンフルール 1922年6月
Photographie J H Lartigue(c)Ministère de la Culture - France / AAJHL
植田正治は、あらかじめ演出してから撮影した作品が印象的です。
金子「植田正治の写真は人間を撮っていても、人として撮るんじゃなくてオブジェとして撮っているとよく言われます。砂丘のシリーズはまさにその典型ですね。彼は、写真の中に自分の生活すべてをはめ込んでいった。だから家族はオブジェのように見えるんじゃないかと思います。また、アマチュア写真家として、生涯、故郷の山陰地方に生きることにもこだわっていました」
 |
植田正治 風船を持った自画像(II)1948年頃
自由に写真制作に没頭していたからこそ、それぞれの生き方が、作品にも反映されているのですね。では、二人の作品に共通する魅力とは何でしょうか?
金子「ラルティーグと植田正治の作品は、こどもでも分かる写真だと思います。写真は記録道具ではありますが、彼らにとっては遊び道具であり、写真を撮ることが遊びとしてあった。つまり、こどもが撮るように、純粋で自由な気持ちで写真にむかっていたんです。だから、こどもの心を持たずに見ると、面白さが半減してしまうかもしれないですね。内容に理由をもとめたら魅力が分からなくなってしまう」
今回の二人展は、見る側の純粋さが試される展覧会ということになりますか(笑)。
金子「この展覧会がどれだけ楽しめるかは、どれだけ自分の心が自由であるかにかかっていると(笑)。これは冗談だとしても、とにかくこの二人の作品は理屈ぬきに楽しい写真が多いので、美術館だからといった気構えや難しいうんちくは抜きにして、気楽に楽しんでいただけたら企画者としてこれ以上の幸せはありません」
(2013年8月インタビュー) 構成=富田秋子