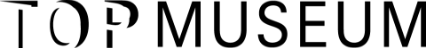News
北野 謙 <作家インタビュー>
内と外の世界を見せる
赤ちゃんのフォトグラム
「イメージの洞窟:意識の源を探る」展にはバックグラウンドの異なるさまざまな作家たちの作品が展示されます。そこで、展示を準備中の出品作家にご登場いただき、作家自身の言葉で作品について、「イメージの洞窟:意識の源を探る」展についてお話しをうかがいました。
北野謙さんは、ある集団に属する人々のポートレートを重ね焼きした〈our face〉や、長時間露光による都市写真〈溶游する都市〉、屋上に設置したカメラのシャッターを半年間開け続ける〈光を集めるプロジェクト〉などの作品で知られます。今回、展示する作品は赤ちゃんを印画紙の上にのせて光を当てて制作したフォトグラム〈未来の他者〉。いったいどのような作品なのでしょうか。 (インタビュー・文=タカザワケンジ)

北野謙 《N1》〈未来の他者〉より 2018年 フォトグラム 作家蔵 ©Ken Kitano, courtesy MEM
──〈未来の他者〉を拝見して、こんな赤ちゃん写真は見たことがない、と驚きました。赤ちゃんのフォトグラム、という発想の斬新さもさることながら、得られたイメージの生々しいこと。真新しい生命の力を感じると同時に、自分もこんな感じだったのかな、と思ったりもしました。
北野■“自分のこと感”があるでしょう?写真の力の本質って、人ごとでないと感じる、内発的な共感だと思うんですよね。
──北野さんと赤ちゃんという組み合わせで思い出すのは、2017年に埼玉県立近代美術館で展示された〈未来の他者〉です。今回展示される作品と同じタイトルですが、こちらは赤ちゃんの全身ポートレートを重ね焼きするという、北野さんの代表作〈our face〉の手法で作られています。そもそも赤ちゃんをモティーフにした作品を作ろうと思われたのはなぜでしょう。
北野■きっかけは東京都写真美術館の「日本の新進作家展vol.10 写真の飛躍」(2011)に出品したことでした。あるレディースクリニックの院長先生が、僕の作品を見てくれて、人づてに連絡をくれたんです。赤ちゃんの作品を作ることに興味はないですか、と。でも、そのときは唐突だなと感じてしまって、返事を保留しておいたんです。
2014年頃、もう1度人づてにご連絡いただいて、じゃあ、一回会いにいってみようとクリニックにうかがったら、病院も先生も考え方がすばらしかった。
先生はこんなことをおっしゃっていました。「医療を通じて、この世界にはいろいろな事情があって生まれてくる命があると日々感じています。北野さんの〈our face〉は、芸術でそれと同じことを表現しているのではないかと思いました。何か一緒にできませんか?」。そこまで言われたら「はい、やります」と言いますよね(笑)。実際、すごく嬉しかったですし。
それから、週のはじめに電話してアポを取り、生まれたばかりの赤ちゃんの撮影にうかがうということをしばらく続けました。クリニックに行くたびに、数時間前までお腹の中にいた命と出会い、彼らがこちらの世界にやってきたんだ、とひしひしと感じました。
──それが埼玉県立近代美術館で発表した、重ね焼きの〈未来の他者〉になったんですね。今回、フォトグラムの〈未来の他者〉へと発展したきっかけはどのようなものだったのでしょうか。
北野■重ね焼きの〈未来の他者〉のプリントを大きく引き伸ばしたかったので、東京造形大の広い暗室を借りました。現像液の中で印画紙の上に赤ちゃんのイメージが浮かび上がってくるのを見て、手伝ってくれた学生が「羊水の中で赤ちゃんが気持ちよさそうに泳いでいるみたいですね」と言ったんです。それを聞いて「ということは、印画紙の上に赤ちゃんはのるんだ。なんでフォトグラムにしなかったんだろう」と思ったんです。

制作風景
──フォトグラムですから、印画紙の上に赤ちゃんをつれてきて露光させる。原寸大ということになりますが、撮影はどのようにされたのでしょうか。
北野■撮影は東京造形大のスタジオでおこないました。周りに赤ちゃんが生まれたばかりの友人たちが何人かいたので、その子たちや、知り合いの伝手をたどってモデルにとお願いしました。
赤ちゃんを寝かせることができるように、撮影スタジオに畳を敷いて、蒲団を敷きました。壁を作って撮影用の完全暗室を作り、印画紙を敷いて、その上に赤ちゃんにのってもらいました。
真っ暗な中で、赤ちゃんを印画紙の上にのせてもらったのですが、親御さんが手を離した瞬間に「ぎゃーっ」と大泣き。阿鼻叫喚でした(笑)。パシャってストロボを焚いて、抱き上げてください、と。
──何カ月くらいの月齢の赤ちゃんを、何人撮影したのでしょうか。
北野■2カ月から8カ月くらいの赤ちゃんを8人撮影しました。首が据わってハイハイするまでですね。最初は3人来てもらって、1人だけ、2人だけ、3人で、と撮影しました。2回目は5人に来てもらいました。だから5人で写っている作品もあります。
──フォトグラムでは印画紙に光が当たった部分は真っ黒になります。北野さんは今回、フォトグラム作品をネガとして、それを反転させたポジ像もお作りになったんですよね。
北野■黒い背景に像が浮かんでいるイメージだけではなく、明るいところに赤ちゃんがいるところを見てみたかった。それに、反転させると色も転ぶので、色を変えることで違う発見があるかもしれないと期待しました。
やり方としては、フォトグラムの下に未露光の印画紙を置いて、上からストロボを発光させます。そのとき、ストロボの前にフィルターを入れて色をコントロールしています。フィルターを入れないと、茶色っぽいにごった色になる。僕なりのいちばんしっくりする色はどんな色かを考えながら、フィルターを変えていろいろなテストデータを作りました。結局、濃いグリーンを何枚も重ねて、赤ちゃんが淡いピンクになるようにしています。白地に赤という組み合わせがぴったりだったんです。
──「イメージの洞窟:意識の源を探る」というテーマとの関連性で言えば、赤ちゃんのいる場所─お母さんのお腹の中─を身体の中の洞窟と考えることもできそうです。
北野■お母さんのお腹の中と、こちら側の世界。内と外のイメージを展示方法で表現できそうです。具体的には、暗めにして作品にだけ光を当てるネガ像の部屋と、その外側に、壁に赤の補色にあたる青を使った明るい空間を作り、サーモンピンク色の赤ちゃんのポジ像を展示するというものになりそうです。
──洞窟というテーマについて、いま、思われていることを教えてください。
北野■洞窟は大昔から人間にインスピレーションを与えてきた場所だと思いますね。数万年前にラスコーやアルタミラのような洞窟壁画を描いた人たちがいたように。あの洞窟壁画を描いた人たちは、まさか数万年後の人類がその絵を見ることになるとは思っていなかったと思います。でも、僕たちはその絵を見ていろいろなことを考えることができる。写真もまた、そんなふうに彼方の他者とイメージの回路を結ぶことができるメディアだと思っています。
僕自身、いま生きている人たちだけでなく、時間的にも距離的にも遠く離れた他者を想定して、彼らに向けて表現していきたいと思っているんです。芸術はそれくらいの遠いオーディエンスを想定したほうがいい。遠ければ遠いほど、多様な解釈の可能性が広がりますから。とくに今回は洞窟という抽象性の高いテーマの展覧会なので、作品をめぐっていろいろな話しができるんじゃないかと楽しみにしています。
(2019年7月)
「イメージの洞窟:意識の源を探る」展 詳細はこちら
赤ちゃんのフォトグラム
「イメージの洞窟:意識の源を探る」展にはバックグラウンドの異なるさまざまな作家たちの作品が展示されます。そこで、展示を準備中の出品作家にご登場いただき、作家自身の言葉で作品について、「イメージの洞窟:意識の源を探る」展についてお話しをうかがいました。
北野謙さんは、ある集団に属する人々のポートレートを重ね焼きした〈our face〉や、長時間露光による都市写真〈溶游する都市〉、屋上に設置したカメラのシャッターを半年間開け続ける〈光を集めるプロジェクト〉などの作品で知られます。今回、展示する作品は赤ちゃんを印画紙の上にのせて光を当てて制作したフォトグラム〈未来の他者〉。いったいどのような作品なのでしょうか。 (インタビュー・文=タカザワケンジ)

北野謙 《N1》〈未来の他者〉より 2018年 フォトグラム 作家蔵 ©Ken Kitano, courtesy MEM
──〈未来の他者〉を拝見して、こんな赤ちゃん写真は見たことがない、と驚きました。赤ちゃんのフォトグラム、という発想の斬新さもさることながら、得られたイメージの生々しいこと。真新しい生命の力を感じると同時に、自分もこんな感じだったのかな、と思ったりもしました。
北野■“自分のこと感”があるでしょう?写真の力の本質って、人ごとでないと感じる、内発的な共感だと思うんですよね。
──北野さんと赤ちゃんという組み合わせで思い出すのは、2017年に埼玉県立近代美術館で展示された〈未来の他者〉です。今回展示される作品と同じタイトルですが、こちらは赤ちゃんの全身ポートレートを重ね焼きするという、北野さんの代表作〈our face〉の手法で作られています。そもそも赤ちゃんをモティーフにした作品を作ろうと思われたのはなぜでしょう。
北野■きっかけは東京都写真美術館の「日本の新進作家展vol.10 写真の飛躍」(2011)に出品したことでした。あるレディースクリニックの院長先生が、僕の作品を見てくれて、人づてに連絡をくれたんです。赤ちゃんの作品を作ることに興味はないですか、と。でも、そのときは唐突だなと感じてしまって、返事を保留しておいたんです。
2014年頃、もう1度人づてにご連絡いただいて、じゃあ、一回会いにいってみようとクリニックにうかがったら、病院も先生も考え方がすばらしかった。
先生はこんなことをおっしゃっていました。「医療を通じて、この世界にはいろいろな事情があって生まれてくる命があると日々感じています。北野さんの〈our face〉は、芸術でそれと同じことを表現しているのではないかと思いました。何か一緒にできませんか?」。そこまで言われたら「はい、やります」と言いますよね(笑)。実際、すごく嬉しかったですし。
それから、週のはじめに電話してアポを取り、生まれたばかりの赤ちゃんの撮影にうかがうということをしばらく続けました。クリニックに行くたびに、数時間前までお腹の中にいた命と出会い、彼らがこちらの世界にやってきたんだ、とひしひしと感じました。
──それが埼玉県立近代美術館で発表した、重ね焼きの〈未来の他者〉になったんですね。今回、フォトグラムの〈未来の他者〉へと発展したきっかけはどのようなものだったのでしょうか。
北野■重ね焼きの〈未来の他者〉のプリントを大きく引き伸ばしたかったので、東京造形大の広い暗室を借りました。現像液の中で印画紙の上に赤ちゃんのイメージが浮かび上がってくるのを見て、手伝ってくれた学生が「羊水の中で赤ちゃんが気持ちよさそうに泳いでいるみたいですね」と言ったんです。それを聞いて「ということは、印画紙の上に赤ちゃんはのるんだ。なんでフォトグラムにしなかったんだろう」と思ったんです。

制作風景
──フォトグラムですから、印画紙の上に赤ちゃんをつれてきて露光させる。原寸大ということになりますが、撮影はどのようにされたのでしょうか。
北野■撮影は東京造形大のスタジオでおこないました。周りに赤ちゃんが生まれたばかりの友人たちが何人かいたので、その子たちや、知り合いの伝手をたどってモデルにとお願いしました。
赤ちゃんを寝かせることができるように、撮影スタジオに畳を敷いて、蒲団を敷きました。壁を作って撮影用の完全暗室を作り、印画紙を敷いて、その上に赤ちゃんにのってもらいました。
真っ暗な中で、赤ちゃんを印画紙の上にのせてもらったのですが、親御さんが手を離した瞬間に「ぎゃーっ」と大泣き。阿鼻叫喚でした(笑)。パシャってストロボを焚いて、抱き上げてください、と。
──何カ月くらいの月齢の赤ちゃんを、何人撮影したのでしょうか。
北野■2カ月から8カ月くらいの赤ちゃんを8人撮影しました。首が据わってハイハイするまでですね。最初は3人来てもらって、1人だけ、2人だけ、3人で、と撮影しました。2回目は5人に来てもらいました。だから5人で写っている作品もあります。
──フォトグラムでは印画紙に光が当たった部分は真っ黒になります。北野さんは今回、フォトグラム作品をネガとして、それを反転させたポジ像もお作りになったんですよね。
北野■黒い背景に像が浮かんでいるイメージだけではなく、明るいところに赤ちゃんがいるところを見てみたかった。それに、反転させると色も転ぶので、色を変えることで違う発見があるかもしれないと期待しました。
やり方としては、フォトグラムの下に未露光の印画紙を置いて、上からストロボを発光させます。そのとき、ストロボの前にフィルターを入れて色をコントロールしています。フィルターを入れないと、茶色っぽいにごった色になる。僕なりのいちばんしっくりする色はどんな色かを考えながら、フィルターを変えていろいろなテストデータを作りました。結局、濃いグリーンを何枚も重ねて、赤ちゃんが淡いピンクになるようにしています。白地に赤という組み合わせがぴったりだったんです。
──「イメージの洞窟:意識の源を探る」というテーマとの関連性で言えば、赤ちゃんのいる場所─お母さんのお腹の中─を身体の中の洞窟と考えることもできそうです。
北野■お母さんのお腹の中と、こちら側の世界。内と外のイメージを展示方法で表現できそうです。具体的には、暗めにして作品にだけ光を当てるネガ像の部屋と、その外側に、壁に赤の補色にあたる青を使った明るい空間を作り、サーモンピンク色の赤ちゃんのポジ像を展示するというものになりそうです。
──洞窟というテーマについて、いま、思われていることを教えてください。
北野■洞窟は大昔から人間にインスピレーションを与えてきた場所だと思いますね。数万年前にラスコーやアルタミラのような洞窟壁画を描いた人たちがいたように。あの洞窟壁画を描いた人たちは、まさか数万年後の人類がその絵を見ることになるとは思っていなかったと思います。でも、僕たちはその絵を見ていろいろなことを考えることができる。写真もまた、そんなふうに彼方の他者とイメージの回路を結ぶことができるメディアだと思っています。
僕自身、いま生きている人たちだけでなく、時間的にも距離的にも遠く離れた他者を想定して、彼らに向けて表現していきたいと思っているんです。芸術はそれくらいの遠いオーディエンスを想定したほうがいい。遠ければ遠いほど、多様な解釈の可能性が広がりますから。とくに今回は洞窟という抽象性の高いテーマの展覧会なので、作品をめぐっていろいろな話しができるんじゃないかと楽しみにしています。
(2019年7月)
「イメージの洞窟:意識の源を探る」展 詳細はこちら