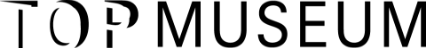News
宮本隆司 スペシャル・インタビュー
都市とシマをめぐる旅は
やがて〝いまだ見えざるところ〟へ
ネパールの山奥で中世そのままの暮らしを続ける城塞都市、活気溢れる東南アジア、中国の街、かつてこの場所にあったビール工場、天に向かって伸びゆく工事中の東京スカイツリー。都市のさまざまな側面をめぐったあと、私たちは「シマ」と題された部屋へと吸い込まれていきます。これまで都市の風景を主題にした作品を発表してきた宮本隆司さんですが、今回、初めて、近年取り組んでいる徳之島の作品を同時に展示しています。豊かな自然に恵まれた徳之島と、アジアの都市とはどのようなつながりがあるのでしょうか。撮影と展示方法についてお話しをうかがいました。
(インタビュー・文=タカザワケンジ)

《面縄ピンホール2013》 2013年 東京都写真美術館蔵
──「宮本隆司 いまだ見えざるところ」展は2部構成になっています。前半はアジアや日本の都市(「都市をめぐって」)、後半は徳之島で撮影した作品(「シマというところ」)です。宮本さんは『建築の黙示録』や『九龍城砦』など、都市をモティーフとする作品がよく知られていますが、なぜ徳之島で作品を制作することになったのでしょうか。
宮本■まず私と徳之島との関わりからお話ししたいのですが、徳之島は私の両親の生まれ故郷なんです。私自身は東京生まれですが、生後4カ月で母と姉と一緒に徳之島に行き、2歳過ぎに東京に戻るまで徳之島に住んでいました。しかし記憶はありません。たしかに徳之島の風景を見ていたはずなのに憶えていない。それでこの展覧会のタイトルを「いまだ見えざるところ」としました。象徴的なのは図録の表紙にもなっている写真です。 小屋のように大きなピンホールカメラをつくり、その中に私自身が入って撮影しました。針穴(ピンホール)を通って入って来た光がカメラの中のフィルムを感光させてできたイメージです。そのため、箱の展開図のような写真になりました。下の黒いシルエットは私です(笑)。
──ご自身でカメラの中に入るとは! 大がかりですね。
宮本■見ていたはずなのに憶えていない光景を何とかして見てみたい。そう思って手間のかかることをしてみたわけです。カメラを置いたのは父の実家の前の海岸で、私が徳之島に住んでいた時に遊んでいたと親戚から聞いています。カメラの中に入って寝そべっていると、その頃の光景が思い出されるような気がしました。

2階展示室前ロビーには、実際に使用されたピンホール・カメラが展示され、ビデオでも撮影の様子が紹介されている。

〈サトウキビ〉 2018年 作家蔵 ©Ryuji Miyamoto Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
──では徳之島のシリーズのもくろみの1つは、見ていたはずの光景を「見よう」という試みなんですね。
宮本■「初源の光景」というのかな。生まれて初めて見た光景の記憶を持っている人がいないように、誰にでも見たはずなのに憶えていない光景があるはずです。しかもそれが妙に気になる。私の場合はそれが徳之島の風景でした。しかも当時の徳之島は米軍の統治下にあり(1953年まで)、物資も乏しく、写真も残っていないんです。
──一方、徳之島の写真と呼応しているのが都市のシリーズです。自然豊かな徳之島とは対照的にも見えますが、このような構成にしたのはなぜでしょう。
宮本■タイトルにまつわる話がもう1つあります。「いまだ見えざるところ」の英訳を「Invisible Land」としました。その言葉からイタリアの小説家、イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』を連想し、都市のパートがはっきりとした意味を持ったんです。『見えない都市』は『東方見聞録』のマルコ・ポーロがフビライ・カンに自分が歩いてきた都市について語るという設定で書かれた幻想的な物語なのですが、「東方の市」はマルコ・ポーロが歩いた町と少しダブっていますし、ロー・マンタンはマルコ・ポーロが旅したシルクロードの街を思わせます。これらは私にとっての「見えない都市」ではないかと思ったわけです。
──マルコ・ポーロの時代には写真はありませんでしたから想像するほかはない。そういう意味でも「見えない都市」ですね。ほかに「建築の黙示録」と「塔と柱」が都市のパートにありますが、こちらはどのように選んだのでしょうか。
宮本■日本の公立美術館での個展は2004年の「壊れゆくもの・生まれいずるもの」(世田谷美術館)に続いて2度目なのですが、今回はその時に展示した写真は1枚もありません。「建築の黙示録」から選んだのは、この美術館ができる前にここにあったビール工場が解体されている写真です。

《サッポロビール恵比寿工場》〈建築の黙示録〉より 1990年 作家蔵 ©Ryuji Miyamoto Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film

〈Lo Manthang(ロー・マンタン) 1996〉より 1996年 東京都写真美術館蔵
──では、今回、香港の高層スラム街を撮影した「九龍城砦」が展示されていないのは、世田谷美術館で展示されたからですか。
宮本■それもありますし、去年、この美術館でお見せしたばかりなので(「建築×写真 ここのみに在る光」展)。ですが、アジアの都市という点で「東方の市」とも共通点がありますし、「ロー・マンタン1996」とピッタリ重なる部分があるんです。どういうことかというと、ロー・マンタンと九龍城砦はどちらも城塞都市なんですね。ロー・マンタンは中世のアジアの城塞都市がそのまま残っていますから、ある意味で九龍城砦の原型とも言えます。
──ロー・マンタンはいまでは世界遺産候補になり、観光客の受け入れも進んでいるらしいですが、宮本さんが訪れた当時は知る人ぞ知る秘境でした。貴重な写真でもありますね。また、都市の作品の中でもっとも新しいものが東京スカイツリーを撮影した「塔と柱」です。なぜ撮影されたんでしょうか。
宮本■スイスのペーター・オルベというピンホールカメラ作家が、自作のカメラを送るから作品をつくってほしいという誘いを受けて撮った作品です。ちょうど東京スカイツリーが工事中で、立ち上がっているところでした。その光景を見て、思い出したのはトリノの「モーレ・アントネリアーナ」。シュルレアリスムの画家、ジョルジョ・デ・キリコがこの「モーレ」を描いた絵があってもともと好きだったんです。それで東京スカイツリーを塔に見立てて、ピンホールカメラで撮ってみようと思いました。

〈塔と柱〉より 2011年 作家蔵 ©Ryuji Miyamoto Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
──宮本さんにはピンホールカメラを使った作品がいくつかありますが、どんなところに魅力をお感じですか。
宮本■ピンホールカメラは不自由なカメラのように思われがちですが、実は制約がないとも言えるんです。ピントという概念がないし、フレーミングもはっきりしない。すべてを受け入れ、ありのままを写す。すると、思わぬものが入り込んできます。おそらく最初期の写真はそういうものだったと思うんですよ。そして、それは赤ん坊が初源の光景を見ることと同じじゃないかと思うんです。赤ん坊は見えるものをありのままに受け入れるし、何が見たいとか、何が重要とかの判断もないはずですから。
──なるほど。「写る」ことに感動する。それはいまのデジカメやスマホでは体験できないことですね。しかもスカイツリーは見ることができても、できあがっていく途中を見ることはもうできない。ほかの都市の作品と同様、もはや「見えざる都市」というわけですね。しかもその対面に、建築物の終わりであるビール工場跡の写真があることも示唆的です。そして、いよいよ「シマというところ」へと続きます。
宮本■「シマ」は、アイランドの島ではなく集落のこと。奄美地方ではそう言います。徳之島はいまでも小さな共同体(シマ)の団結力が強くて、昔ながらのお祭りも残っています。写真にありますが、浜に木や竹を使って家の原型のような「ヤドゥリ」をつくり、一族が集まって宴会をする。かまどに見立てたものにお酒をかけて清めたりもします。そしてその夜に、家々を回って、朝まで踊る。人間のやることは一緒に働く、食べる、踊る、寝ること。徳之島ではいまでもそれがシンプルなかたちで見えるんです。

《井之川》〈シマというところ〉より 2014年 作家蔵 ©Ryuji Miyamoto Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
──建築のパートでは1点ずつ写真をじっくり見ていく展示方法を採られていますが、シマのパートでは会場の空間を意識させるインスタレーションになっていますね。
宮本■できるだけゆるやかに、海風が吹き抜けるような感じにしたいと思いました。モニターを使い、風に揺れるサトウキビの様子をスライドショー形式で見せているのは風を感じてほしいからです。その反対側に私がカメラの中に入って撮ったピンホールの写真を置き、全体を引いた視点で見てもらえるようにしています。ソテツは徳之島の自然の象徴。ポートレートは集落別に構成しています。2014年に私がディレクターを務めた「徳之島アートプロジェクト」というアート・イベントが開かれたのですが、その時に島の公民館で展示した写真がほとんどです。ご本人たちに写真を見ていただいて好評でした。
──展覧会を拝見して、シマも都市も人間が暮らすためにつくってきたものだという共通点が見えてきました。平成から令和へと時代の変化を感じさせるいま、人の暮らしと環境、コミュニティについて考えるきっかけになると感じました。ぜひ、多くの人に見てほしいと思います。

「宮本隆司 いまだ見えざるところ」展 詳細はこちら
やがて〝いまだ見えざるところ〟へ
ネパールの山奥で中世そのままの暮らしを続ける城塞都市、活気溢れる東南アジア、中国の街、かつてこの場所にあったビール工場、天に向かって伸びゆく工事中の東京スカイツリー。都市のさまざまな側面をめぐったあと、私たちは「シマ」と題された部屋へと吸い込まれていきます。これまで都市の風景を主題にした作品を発表してきた宮本隆司さんですが、今回、初めて、近年取り組んでいる徳之島の作品を同時に展示しています。豊かな自然に恵まれた徳之島と、アジアの都市とはどのようなつながりがあるのでしょうか。撮影と展示方法についてお話しをうかがいました。
(インタビュー・文=タカザワケンジ)

《面縄ピンホール2013》 2013年 東京都写真美術館蔵
──「宮本隆司 いまだ見えざるところ」展は2部構成になっています。前半はアジアや日本の都市(「都市をめぐって」)、後半は徳之島で撮影した作品(「シマというところ」)です。宮本さんは『建築の黙示録』や『九龍城砦』など、都市をモティーフとする作品がよく知られていますが、なぜ徳之島で作品を制作することになったのでしょうか。
宮本■まず私と徳之島との関わりからお話ししたいのですが、徳之島は私の両親の生まれ故郷なんです。私自身は東京生まれですが、生後4カ月で母と姉と一緒に徳之島に行き、2歳過ぎに東京に戻るまで徳之島に住んでいました。しかし記憶はありません。たしかに徳之島の風景を見ていたはずなのに憶えていない。それでこの展覧会のタイトルを「いまだ見えざるところ」としました。象徴的なのは図録の表紙にもなっている写真です。 小屋のように大きなピンホールカメラをつくり、その中に私自身が入って撮影しました。針穴(ピンホール)を通って入って来た光がカメラの中のフィルムを感光させてできたイメージです。そのため、箱の展開図のような写真になりました。下の黒いシルエットは私です(笑)。
──ご自身でカメラの中に入るとは! 大がかりですね。
宮本■見ていたはずなのに憶えていない光景を何とかして見てみたい。そう思って手間のかかることをしてみたわけです。カメラを置いたのは父の実家の前の海岸で、私が徳之島に住んでいた時に遊んでいたと親戚から聞いています。カメラの中に入って寝そべっていると、その頃の光景が思い出されるような気がしました。

2階展示室前ロビーには、実際に使用されたピンホール・カメラが展示され、ビデオでも撮影の様子が紹介されている。

〈サトウキビ〉 2018年 作家蔵 ©Ryuji Miyamoto Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
──では徳之島のシリーズのもくろみの1つは、見ていたはずの光景を「見よう」という試みなんですね。
宮本■「初源の光景」というのかな。生まれて初めて見た光景の記憶を持っている人がいないように、誰にでも見たはずなのに憶えていない光景があるはずです。しかもそれが妙に気になる。私の場合はそれが徳之島の風景でした。しかも当時の徳之島は米軍の統治下にあり(1953年まで)、物資も乏しく、写真も残っていないんです。
──一方、徳之島の写真と呼応しているのが都市のシリーズです。自然豊かな徳之島とは対照的にも見えますが、このような構成にしたのはなぜでしょう。
宮本■タイトルにまつわる話がもう1つあります。「いまだ見えざるところ」の英訳を「Invisible Land」としました。その言葉からイタリアの小説家、イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』を連想し、都市のパートがはっきりとした意味を持ったんです。『見えない都市』は『東方見聞録』のマルコ・ポーロがフビライ・カンに自分が歩いてきた都市について語るという設定で書かれた幻想的な物語なのですが、「東方の市」はマルコ・ポーロが歩いた町と少しダブっていますし、ロー・マンタンはマルコ・ポーロが旅したシルクロードの街を思わせます。これらは私にとっての「見えない都市」ではないかと思ったわけです。
──マルコ・ポーロの時代には写真はありませんでしたから想像するほかはない。そういう意味でも「見えない都市」ですね。ほかに「建築の黙示録」と「塔と柱」が都市のパートにありますが、こちらはどのように選んだのでしょうか。
宮本■日本の公立美術館での個展は2004年の「壊れゆくもの・生まれいずるもの」(世田谷美術館)に続いて2度目なのですが、今回はその時に展示した写真は1枚もありません。「建築の黙示録」から選んだのは、この美術館ができる前にここにあったビール工場が解体されている写真です。

《サッポロビール恵比寿工場》〈建築の黙示録〉より 1990年 作家蔵 ©Ryuji Miyamoto Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film

〈Lo Manthang(ロー・マンタン) 1996〉より 1996年 東京都写真美術館蔵
──では、今回、香港の高層スラム街を撮影した「九龍城砦」が展示されていないのは、世田谷美術館で展示されたからですか。
宮本■それもありますし、去年、この美術館でお見せしたばかりなので(「建築×写真 ここのみに在る光」展)。ですが、アジアの都市という点で「東方の市」とも共通点がありますし、「ロー・マンタン1996」とピッタリ重なる部分があるんです。どういうことかというと、ロー・マンタンと九龍城砦はどちらも城塞都市なんですね。ロー・マンタンは中世のアジアの城塞都市がそのまま残っていますから、ある意味で九龍城砦の原型とも言えます。
──ロー・マンタンはいまでは世界遺産候補になり、観光客の受け入れも進んでいるらしいですが、宮本さんが訪れた当時は知る人ぞ知る秘境でした。貴重な写真でもありますね。また、都市の作品の中でもっとも新しいものが東京スカイツリーを撮影した「塔と柱」です。なぜ撮影されたんでしょうか。
宮本■スイスのペーター・オルベというピンホールカメラ作家が、自作のカメラを送るから作品をつくってほしいという誘いを受けて撮った作品です。ちょうど東京スカイツリーが工事中で、立ち上がっているところでした。その光景を見て、思い出したのはトリノの「モーレ・アントネリアーナ」。シュルレアリスムの画家、ジョルジョ・デ・キリコがこの「モーレ」を描いた絵があってもともと好きだったんです。それで東京スカイツリーを塔に見立てて、ピンホールカメラで撮ってみようと思いました。

〈塔と柱〉より 2011年 作家蔵 ©Ryuji Miyamoto Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
──宮本さんにはピンホールカメラを使った作品がいくつかありますが、どんなところに魅力をお感じですか。
宮本■ピンホールカメラは不自由なカメラのように思われがちですが、実は制約がないとも言えるんです。ピントという概念がないし、フレーミングもはっきりしない。すべてを受け入れ、ありのままを写す。すると、思わぬものが入り込んできます。おそらく最初期の写真はそういうものだったと思うんですよ。そして、それは赤ん坊が初源の光景を見ることと同じじゃないかと思うんです。赤ん坊は見えるものをありのままに受け入れるし、何が見たいとか、何が重要とかの判断もないはずですから。
──なるほど。「写る」ことに感動する。それはいまのデジカメやスマホでは体験できないことですね。しかもスカイツリーは見ることができても、できあがっていく途中を見ることはもうできない。ほかの都市の作品と同様、もはや「見えざる都市」というわけですね。しかもその対面に、建築物の終わりであるビール工場跡の写真があることも示唆的です。そして、いよいよ「シマというところ」へと続きます。
宮本■「シマ」は、アイランドの島ではなく集落のこと。奄美地方ではそう言います。徳之島はいまでも小さな共同体(シマ)の団結力が強くて、昔ながらのお祭りも残っています。写真にありますが、浜に木や竹を使って家の原型のような「ヤドゥリ」をつくり、一族が集まって宴会をする。かまどに見立てたものにお酒をかけて清めたりもします。そしてその夜に、家々を回って、朝まで踊る。人間のやることは一緒に働く、食べる、踊る、寝ること。徳之島ではいまでもそれがシンプルなかたちで見えるんです。

《井之川》〈シマというところ〉より 2014年 作家蔵 ©Ryuji Miyamoto Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
──建築のパートでは1点ずつ写真をじっくり見ていく展示方法を採られていますが、シマのパートでは会場の空間を意識させるインスタレーションになっていますね。
宮本■できるだけゆるやかに、海風が吹き抜けるような感じにしたいと思いました。モニターを使い、風に揺れるサトウキビの様子をスライドショー形式で見せているのは風を感じてほしいからです。その反対側に私がカメラの中に入って撮ったピンホールの写真を置き、全体を引いた視点で見てもらえるようにしています。ソテツは徳之島の自然の象徴。ポートレートは集落別に構成しています。2014年に私がディレクターを務めた「徳之島アートプロジェクト」というアート・イベントが開かれたのですが、その時に島の公民館で展示した写真がほとんどです。ご本人たちに写真を見ていただいて好評でした。
──展覧会を拝見して、シマも都市も人間が暮らすためにつくってきたものだという共通点が見えてきました。平成から令和へと時代の変化を感じさせるいま、人の暮らしと環境、コミュニティについて考えるきっかけになると感じました。ぜひ、多くの人に見てほしいと思います。

「宮本隆司 いまだ見えざるところ」展 詳細はこちら