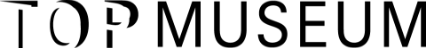News
杉浦邦恵 スペシャルインタビュー
「杉浦邦恵 うつくしい実験 ニューヨークとの50年」(2018年7月24日~9月24日)は、67年からニューヨークを拠点に活動してきた杉浦邦恵の、日本国内における初の本格的な回顧展となる。
先進的な試みを実践してきた彼女に、写真メディアの可能性を見出した留学時代や、作家人生におけるターニングポイント、ニューヨークでのキーパーソンたちとの出会いについて伺った。
(2018年5月 インタビューと文 富田秋子)

孤 #4-V2/2 1967年 発色現像方式印画 東京都写真美術館蔵
“実験”に没頭した学生時代
Q)1963年に渡米されて、シカゴ・アート・インスティチュートに入学されましたね。写真を始めたのは、このときからですか?
杉浦邦恵(以下 K)学科は2年生から専攻することになっていたので、最初はインダストリアルデザインに進もうと思っていたんですが、1年生の間にアートに目覚めたんです。そのとき、写真科の先生二人が、ファインアート(芸術)として写真を専攻しないかとしきりに勧めてくれたんですよ。結局、専攻した学部生は私一人でした。
Q)ジャーナリズムやドキュメンタリーではなく、ファインアートとして写真で作品をつくるというのは、アメリカでもまだ珍しかったのではないですか?
K)シカゴ・アート・インスティチュートはシカゴ美術館の附属大学で、すぐ隣にありました。この美術館は写真部門を早期から設置していて、ニューヨーク近代美術館やサンフランシスコ近代美術館とともに、アメリカで写真芸術の分野をリードする存在だったんです。また、そばにあったイリノイ工科大学にはニュー・バウハウスで知られるモホイ=ナジ・ラースローが設立した写真学科がありました。写真専攻に誘ってくださった二人の先生、ケネス・ジョセフソンとフランク・バラサーティは、モホイ=ナジに教わったハリー・キャラハンの生徒だったんです。授業には他の専攻からも学生が来ていましたが、指導はその先生二人が私一人にかかりきりでついてくれていたわけです。思い起こすと、随分と苦労して教えてくださっていたと思います(笑)。
Q)その当時に、「Cko」シリーズを制作されていたんですよね?
K)初めはカラーフィルムや魚眼レンズを使い、タイプCプリント(発色現像方式印画)で制作してみましたが、そのうち自分の想像するイメージを作りたくなり、大学の暗室にあった引伸機を使ってモノクロのフィルムで二重露光をしたり、市松模様を施してみたり、写真の一部を多重露光してイメージをモンタージュしたりもしました。何かプランを立てて実行するというよりは、カメラの操作や、暗室作業などでさまざまな方法を試し、失敗と実験を何回も繰り返していましたね。
Q)まるで理系の大学の授業のようなお話ですね。
K)渡米前に通っていた大学では、物理学を専攻していたんです。物理学者のタイプに実験重視と理論重視の2種類あるとしたら、自分はやはり前者、実験するほうになっていくんだろうなと思っていたんです。だから、私にとっては物理学を写真に置き換えたような感じでした。本当に自分が創造的に作品制作を行えるとすれば、写真技術の基本を一通り習得した後、今度はそのプロセスを崩していくことで、可能性が開けるのではないかと考えていました。

孤 #L9- V1/3 1966年 発色現像方式印画 東京都写真美術館蔵
Q)YouTubeにアップロードされている映像作品 「Requiem(鎮魂歌)」(1966、YouTubeはこちら)には、女性が自分の裸体を抱え込むようなポーズで映っていますが、「Cko」のシリーズで、この映像からモチーフを引用したものもありますか?
K)「Requiem(鎮魂歌)」は、当時、映画の授業もとっていたので、16mmの映画用カメラに魚眼レンズをつけて撮ったものでした。 ちょうど制作が終わった頃に、クラスメイトの黒人男性がミシガン湖で溺れて亡くなったのです。とてもショッキングな出来事で、自殺との憶測もありましたが、真相はわかりませんでした。それで追悼の意味をこめて、鎮魂歌という題名にしたのです。「Cko」シリーズも同時期に制作していましたので、このフィルムのイメージも使っていたと思います。
Q)シリーズ名の「Cko」は、孤独の「孤」にアルファベットを当てたものだそうですが、二十歳で単身アメリカに渡られて、毎日感じていたことが作品に反映されていたんでしょうか?
K)やはり最初の1年は、激しい年でした。シカゴの冬はものすごく寒くなるんですよ。それで、あたたまろうと思ってバスルームに行くと、理由もわからずにワーッと激しく泣き出してしまうこともありました。ホームシックやヒステリーにかかっていたのかもしれないけど、そこで泣いてしまうと、ケロッとして出て来られるんです。でも、学校はとても面白くて、日本に帰ろうとは思いませんでした。
三つのターニングポイント
Q)ご自身の作家活動において、ターニングポイントになった出来事を挙げるとしたら、どんなものがありますか?
K)ニューヨークに移り住んだこと、リチャード・ベラミーに会ったこと、そして9.11アメリカ同時多発テロ事件を経験したことですね。
Q)ニューヨークに移られたのは、大学を卒業した1967年でしたね?
K)旅行で来たことが何度かあって、ずっとここに住みたいと思っていたんです。でも、来てからしばらくは生活の基盤を固めるのでいっぱいでした。学生時代は仕送りや奨学金がありましたが、今度は自分で何とかしないといけなかったので。この頃、コロムビアレコードからフリーランスの仕事をもらったことがあって、レコードジャケットのイメージを何枚か作ったこともあります。


Q)どのような経緯で、アートディーラーのリチャード・ベラミー(通称 ディック・ベラミー)に出会ったのですか?
K)ニューヨークに来てからカラー写真などいくつかの制作方法を試してみたのですが、一番手応えを感じたのが、感光材をカンバスに塗って白黒写真のイメージを定着させるフォトカンバスの手法でした。そこで、作品がある程度たまってきたところで、勇気を振り絞って画廊やアートディーラーたちに連絡し、作品を見せにまわったんです。その頃ソーホーに画廊を開いたばかりだったポーラ・クーパーに作品のスライドを見てもらったところ、彼女が「自分はダウンタウンにいて、(作品の実物を見に)行けないから、アップタウンにいるディック・ベラミーに会いなさい」と、ディックを紹介してくれました。彼は有名なグリーンギャラリーをやめ、小さな画廊の1室を借りて、自分の仕事をやっていたんです。
Q)ディック・ベラミーご本人が杉浦さんのスタジオにいらしたんですか?
K)スライドを見てもらったときに、「あなたのスタジオを訪問したいけど、私が来るのを2年ぐらい待ってる作家もいるから」と言われたので、これでは希望はもてないなと思っていたのですが、それから1週間ぐらいで彼がスタジオに現れたんです。「これはひどい」、「大嫌いだ」と、めちゃくちゃに叩かれました。でも、その時彼は「新しいシリーズを作ったら、もう一回見に戻って来る」とも言ってくれました。なんで彼はそんなひどいことを言うのかと考え、勉強もしました。そして、カンバスのサイズを大きくして、写真の小さなイメージを拡大してみたのです。すると、現実を写しているのに、イメージは抽象的になるんですよ。それを1年かけて制作し、ディックに見せに行ったら、今度はすごくいいと言ってくれたんです。
Q)それが、1971年頃のことですね?
K)その後、今度はディックから紹介されたと、マーシャ・タッカーという方から電話があって、「あなたのスタジオに行きたい」といってきたんです。私は何もわかっていなかったから、なんでそんな人が来たいなんて言うんだろう?なんて思っていたんですけど(笑)、彼女は翌年の3月に予定されていたホイットニーのアニュアル展のキュレーターだったんです。ディックが良いと言ってくれた作品を見せたら、彼女も高く評価してくれて、その1972年の展覧会に作品を出すことができました。
Q)ホイットニーのアニュアル展「1972 Annual exhibition contemporary American painting」は、ニューヨークのホイットニー美術館で毎年開催されていた、新進作家の登竜門としても有名なグループ展でしたよね?
K)ホイットニーのアニュアル展は絵画と彫刻の展覧会が1年おきに開催されていました。私が参加したのは絵のアニュアル展のほうで、72年の展示を最後に翌年からバイアニュアルに変わるんですけど、そのアニュアル展の頃からとても注目されてましたね。これをきっかけに、ニューヨークでまた個展を開催できたんですが、そのときには作品が4、5点ほど売れました。ホイットニーに入ったということが、美術作品を買う方たちに対して価値の保証になるということはあったと思います。

行き止り 小 1977-2009年 フォト・エマルジョン アクリル カンヴァス 東京都写真美術館蔵

ボタニカス8 1989年 ゼラチン・シルバー・プリント 東京都写真美術館蔵
Q)9.11同時多発テロが発生したときには、どこにいらっしゃったんですか?
K)テロが起こったのはわりと朝早くて、その日は、自宅のスタジオで暗室作業をしていたんです。普段、そういうときは電話には出ないんですけど、立て続けにメッセージが入っていたので聞いてみたら、そのうちの一つは日本の友人からで、「大変なことが起きているみたいだからテレビをつけてみて」と言うんです。それで、テレビをつけたら、ちょうどワールドトレードセンターに2機目が突入するところでした。
Q)杉浦さんのスタジオがあるチャイナタウンは、ワールドトレードセンターからそんなに遠くはないですよね?
K)1マイル(1.6km)くらいですね。カナル・ストリートの上空を黒い戦闘機がゴーゴーと音をたてて飛んでいましたし、窓から下をのぞくと、ウォール・ストリートから人がぞろぞろとゾンビみたいに歩いてきていました。人も車も灰を被って真っ白なんです。戦争はこうやって始まるんだろうなと、そのときに思いました。
Q)アーティストとして考え方が変わったところはありましたか?
K)アメリカの本土を空から攻撃されたことは初めてだったからか、人々の拒絶反応は想像以上に大きかったですね。画廊の人もアーティストも、みんなすごく怒っているんですよ。一方で、私のようなアジア人は一方的にどちらかだけが悪いと断罪する気にはならなくて、ムスリムの方々も気の毒に感じてしまうわけです。こういうところから人々の間に亀裂が生じてきてしまうのかもしれないですね。そして、私がそのときに思ったのは、これまでどおり同じ生活をして、アートを作るしかないんだということでした。 同じ年に、個展を開催するために日本に行ったんですけど、そこでしみじみと、「ああ、私は無事なんだ」と思いました。
ニューヨークでの出会い

ボクシングの書類 篠原 Bp3 1999-2000年 ゼラチン・シルバー・プリント
Q)ながらくニューヨークを拠点にされてきましたが、どんなところに魅力を感じていますか?
K)日本にはノスタルジーを強く感じるし、人も自然も繊細で良いところはたくさんありますけど、自分にとってはニューヨークが特別な場所なんです。アメリカの中でも、私はここにしか住めないと思っています。世界中の人が集まってくるから、アメリカのヨーロッパであり、アジアであり、そして世界中でもある。誰もが居心地の良さを感じる、とてもユニークなところだと思います。
Q)90年代から、人物を被写体にした作品制作を開始されていますが、そのきっかけはニューヨークでの篠原有司男氏との出会いだったそうですね。
K)私は日本の美術学校には通っていなかったから、日本人アーティストの方々とはあまり親交がなかったんです。でも、とあるきっかけでぎゅうちゃん(篠原氏)と知り合い、とても気が合って、友人になりました。彼との出会いをきっかけにたくさんの方に助けていただいて、銀座絵画館で日本での初個展(1978年)を開くことができましたし、さらにそこから日本で写真を扱う唯一のギャラリーだったツァイト・フォトの石原悦郎さんにも交流がつながっていきました。
Q)だいぶ後になりますが、96年にツァイト・フォトで開催されたレントゲン写真のシリーズの個展を拝見しました。
K)90年代前半に、私はすごく大きな病気をしたんですよ。肺に穴が開いてしまい、手術をしたんですけど、そのためにたくさんレントゲンを撮ったんですね。それで興味を持って、病気が治ってからレントゲン写真を自分のもの以外もたくさん集めて、印刷したり、プリントしたりして作品にした時期があったんです。でも、レントゲンはちょっと異常な人間の姿だから、今度は普通の人間をモデルにした作品を作りたいとぎゅうちゃんたちに話したら、「自分たちがモデルになるよ」と言ってくれたんです。

(レントゲン)棚のインスタレーション 1994年 ゼラチン・シルバー・プリント アクリル 金属製棚 ワイヤー 作家蔵
Q)それで、篠原さんたちが行っていたボクシング・ペインティングのパフォーマンスを撮影することになったんですね?
K)ただ、撮影するときには彼らが日本に帰っていていなかったから、若い男性二人にモデルになってもらったんです。ぎゅうちゃんたちはニューヨークに戻ってきてから撮ったので、アイデアは彼からインスパイアされたものですが、作品としては2作目になりました。
Q)それが90年代終わり頃のことで、その後、2000年代に「Artists and Scientists(芸術家と科学者)」シリーズの制作が始まるわけですね。
K)周りの人々をモデルにして始めたので、必然的にアーティストを撮ることになりました。また、JGS(Joy of Giving Something)という写真の財団が、DNA構造発見50周年記念のために、科学者の影のポートレートを注文してきたので、芸術家と科学者のシリーズとなったのです。
Q)「Artists and Scientists」はカメラを使わず、壁に感光紙を貼って、その前に人物を配置し、暗闇の中で光を当てることで感光させて撮影を行なったとのこと。その対象ごとに違う演出や小道具も写っていますね。
K)人物を特徴づけるアクションやシンボルを、彼らの影とともに、撮影時からフォトグラムに組み込んだのです。どんな演出にするかは、撮影前にインタビューや電話で、私の意図や彼らからのアイデアを検討して決めていました。

草間彌生 Ap ゼラチン・シルバー・プリント 2003年 国際交流基金所蔵
Q)例えば、草間彌生さんとはどのような感じで撮影されたんですか?
K)彼女がニューヨークで展覧会を開催したときに、私から話しかけたんです。私は『美術手帖』という雑誌で長くニューヨークのアートシーンを紹介する文章を書いていて、草間さんのことを記事にしたこともあったので、彼女も私のことをご存じでいらっしゃいました。 そこでジャスパー・ジョーンズを撮影したばかりだと言ったら、「私もやるわ」と引き受けてくれたんです。一緒に写っているのは、花をつけた透明のビニール傘なんですよ。細江英公さんが撮った短い映像で、草間さんが着物を着てニューヨークの街を歩いているところを撮影した作品があるんですが、それがとても可愛いから、傘に花をつけて撮影したいと言ったら、彼女も賛成してくれました。
Q)作品クレジットによれば、撮影は2003年になりますね?
K)最初に予定していた日は彼女が腰痛でキャンセルになってしまったんです。もうほとんど諦めていたんですけど、2週間ほどしたらアシスタントの方から電話がきて、彼女の体調が良いから今日、明日なら行けますとおっしゃるんです。それで急に撮影できることになったので、また腰が痛くならないようにと、シングルのサイズだけ4枚撮ったんです。
Q)フォトグラムの手法で制作するポートレートは、本人を被写体にしながらも、写真と絵画の要素を併せ持つ、とても象徴的なイメージになっていますね。
K)私はずっと写真で何ができるかと考えてきました。ただそれと同時に、撮ったままプリントするだけでは物足りなかったり、逆に嫌なものが写り込んでいたりするから、どうしても写真イメージに自分のビジョンを入れたくなってしまうところがある。今の言葉でいうと自分のアイデンティティーが出ていない気がするんです。自分は写真家とみなされることが多いですが、正確には写真を使った美術家なんだと思っています。

撮影 石原悦郎
「杉浦邦恵 うつくしい実験 ニューヨークとの50年」展 詳細はこちら