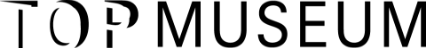トピックス

〈物草拾遺〉より 、1981年
〈物草拾遺〉より 文京区本郷、1981年

須田一政の写真を見ると、自分たちの生きる日常の中に、こんなに強烈な情景があったのかと驚かされずにはいられない。私たちが見えていないもの、見過ごしているものは無数にあり、それをシャッターにとらえて、そして、独自の写真世界に焼き付けるのだ。9月に開催される個展で代表作とともに最新作も出展する予定という須田に、その写真人生や制作の原動力についてお話を伺った。
須田さんはこれまで、1976年に日本写真協会新人賞を受賞された「風姿花伝」や、1983年に日本写真協会年度賞を受賞された「物草拾遺」など、インパクトのある作品を数多く発表されてきていますが、ご自身の作品に対する評論で、それは全然違うと感じることはありますか?
「それは、たえず感じていますよ(笑)。評論とかそういうものには、からめとられたらダメだと思っているんです。ある一定の評価が定まってしまったり、この人はこういう人だとか、作風はこうであると言われちゃうと、自分自身に興味がなくなっちゃうんですよ。これから何を撮っても、そういうふうにしか見られないんだなと思ったら、被写体やテーマに対するときめきがなくなってしまうじゃないですか」
 |
〈風姿花伝〉より 秋田・西馬音内、1976年
では、須田作品を語る時にはよく “日常に潜む闇”や“妖しさ”、もしくは“ハレとケ”といった言葉が使われますが、これにも違和感を感じてしまう?
「それよりも、自分としては、物ってちょっと角度が違うとこんなに面白く見えるのかとか、こんなにぎょっとするような表面に写ってしまうのかといったことに、いつも驚きながら写真を撮ってきましたし、その結果として自分の作品が出来上がってきたと言ったほうが、しっくりきますね。そういう面白さを探して行くことにはいつも興味があったし、それなりに努力もしました。いや、努力はしていないかな(笑)」
 |
 |
〈東京景〉より、1975-78年
そういった、物の見方、撮り方といった部分で、影響を受けた方はいるのですか?
「僕は撮るよりも見るほうから写真に入ったくちで、若い頃はウィリアム・クラインやリチャード・アベドン、アービング・ペンの写真集を、洋書屋に通ってはよく眺めてましたね。
中でもアービング・ペンが僕は大好きなんだけど、自分で写真を撮るようになってから、同じように自分も撮ってみようと思い立ちましてね。ペンの写真集の中にフランスパンとか冷凍食品を配置して撮った静物写真があって、それだったら自分でも発想しやすいと思ってやってみたんだけど、実際に撮ってみたら、構成力も違うし、色の発色も違うし、真似てみたところで似て非なるもので、本物との違いを思い知らされましたね」
今からちょうど50年前、雑誌『日本カメラ』の誌上コンテストで、デビュー作とも言える『恐山』が年度賞を受賞されていますが、やはりこれが本格的に写真の道に進むきっかけとなったのでしょうか?
「気持ちにはずみがついたというのはありましたね。自分の興味のおもむくままに写真を撮っても良いんだと、自信を持つことができたと思います」
この「恐山」は、霊場恐山への旅を記録したものでしたが、旅はその後、作品作りにおいて重要な契機になっていますね。
「その年度賞を受賞したのは23歳の時でしたが、その頃に参加していたアマチュア写真グループでの経験が、自分にとってはとても貴重なものだったと思います。
そのグループは、ぞんねぐるっぺという僕も通っていた東京綜合写真専門学校の一期生が立ち上げた会で、自宅そばの神保町にあったんです。主催者がDP屋を営んでいて、写真集が沢山おいてあったんですが、それが見たくてそのDP屋の前を行ったり来たりしていたら、ゆっくり椅子に座って見たらいいじゃないと声をかけてくださって、写真が好きなの?なんて言われてね。好きですって言ったら、この二階で写真の会をやっているからと見学に誘ってもらったのが、参加したきっかけなんですよ。あの頃、濱谷浩さんの写真集『裏日本』が写真を志す人のバイブルになっていて、今でも僕が北のほうに足がむいちゃうのもその影響が大きいんですが、その会でも、みんなで雪国の写真を撮る旅に出かけたわけです。でも、写真を撮ることだけにきゅうきゅうとするのではなくて、例えば雪の中で、バーナーでコーヒーを淹れて飲んだりしてね。それがまた楽しいんですよ。専門学校ではテクニカルなことを学びましたけど、この会では、そういう旅心というものを教わったと思います。写真も楽しいし、旅も楽しい、そんな風にして、写真の魅力にとりつかれていったんですよね」
 |
〈恐山へ〉より、1970-80年代
1967年から71年まで、前衛劇団の天井桟敷で専属カメラマンをされていましたね。
「主宰の寺山修司さんが書く戯曲が好きだったんですよ。それで、スタッフ募集の広告を見て、写真の記録係として入れてもらえないかと思って応募したんです。まだ劇団が旗揚げしたばかりの時で、10代の少年少女が寺山さんの家に寝泊まりしながら舞台稽古しているんですが、その熱気たるや、すごかったですね。それに、横尾忠則さんや宇野亜喜良さんが美術をやったり、コシノジュンコさんが衣装をやったり、錚々たる才能が寺山さんを取り囲んでましたしね。僕はただ単にくっついていただけなんだけど、その現場にいられたということは、とても貴重な経験だったとしみじみ思いますね。アマチュアのぞんねぐるっぺでは旅の仕方を教わったわけですけれども、天井桟敷ではパッションみたいなもの、一つのものに盲目的に向かうときの熱気を学んだと思います」
 |
 |
〈紅い花〉より、1968-70年代
最新作ではマネキンを被写体にされているとうかがいました。
「マネキンを見ていると、囚われ人というイメージがわいてきてね。マネキンの足は単に機能として立たせるためにあるわけで、そこに留め金がついていたりするんですが、ひょっとしたら、こういうところに純粋なエロスがあるんじゃないかと思うんですよ。早朝の誰もいない時間を狙って、銀座のショーウィンドウを撮影しているんですけど、僕は日中シンクロといって、昼間でもストロボをたくんです。普通はトーンが白っぽく飛んじゃうんですが、それを無理に焼き込むと、写真の画がヌラッと出てきて、その質感がなんとも言えなく良い。そんな出来上がりの画像を想像すると、それだけでドキドキしてきちゃってね。こういうドキドキ感に突き動かされながら、今も写真を撮ってますね」
インタビュー:丹羽晴美(東京都写真美術館 学芸員)
構成:富田秋子