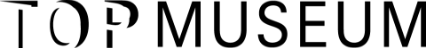トピックス
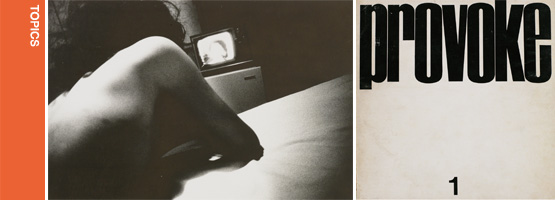
左)森山大道「無題」『プロヴォーク』 季刊第2号より 1969年
右)『プロヴォーク』1号表紙 1968年11月1日

写真はそれだけで成立するものではなく、人々の生き様や思想、様々なカルチャーと密接にかかわり合いながら、ともに立ち上がってくるものなのではないか? そして、その流れは、もしかしたら、ロック、ジャズ、フォーク、ニューミュージックと、各時代を彩った音楽の変遷と似ていると言っても良いかもしれない。1968年。まさに、世界中が革命や社会運動など激動の中にあった時代、他のカルチャーと呼応するように、写真表現は大きな節目を迎え、日本独自の表現が新たに芽吹いた時期でもあった。この年を軸に展覧会を企画した当館の金子隆一専門調査員に、1968年とその時代の写真について、話をきいてみた。
ここ数年、美術館や出版界で日本の1960年代、70年代がさかんに取り上げられています。特に写真作品に対する海外からの注目度が増しているとききました。
「この時代、日本では全共闘(全学共闘会議)を主体とする学生運動が過激さを増して、機動隊が動員されるといった事態に発展したり、強権的な空港建設に異議を唱えた三里塚闘争が社会問題化していました。若い写真家や学生たちは、学生運動であれば学生の側、三里塚であれば闘争する農民の側に立って撮るということが基本的な姿勢であり、だからこそ彼らは当事者に受け入れられて、現場で自由に撮ることができました。ところが、フランスでは1968年にパリ五月革命と呼ばれる反体制運動の嵐がまきおこり、アメリカではベトナム反戦の大規模な運動が繰り広げられていたのに、それらを記録したものは雑誌社や新聞社のカメラマンが撮った報道写真しか残っていないのだそうです」
 |
 |
左)武林盛一 「幌内駅」 1871-1880年頃 右)桑原甲子雄『東京昭和十一年』1935年
「写真100年—日本人による写真表現の歴史展」
1968年、日本写真家協会が開催した、日本の写真史が写真家自身によって体系づけられた展覧会。東松照明を中心に多木浩二、中平卓馬、内藤正敏、松本徳彦らが資料の収集と調査を行った。北海道開拓写真の再評価、桑原甲子雄や植田正治の再発見、アノニマス(無名性)の写真への注目など、日本の写真史に新しい歴史観を構築した。
つまり、当事者の側に立ち、つぶさに記録するという写真のあり方が、図らずも日本独特のものとしてとらえられているということですか?
「そのような写真はアメリカにもフランスにもないそうです。パリ五月革命にしても、学生たちが日々どんなふうに暮らしていて、どんなことが起きていたのか、そういう全体を撮ろうとしたものはないと聞いています。もちろん、当時撮影していた人たちは、目の前にある現実をなんとかしたいという一心でやっていたわけで、日本独特の写真を撮ろうなどと思っていた訳ではないんですが、結果的に、今そのようにとらえられているわけです」
激動の時代の中でも、特に1968年に焦点を当てた展覧会を企画された目的は何なのでしょう?
「本展で取り組みたいのは、実は写真の表現の問題ではないんです。それよりも、写真というものが、どういう状況の中で成り立っているのか、その枠組みを解き明かすことができたら良いなと思っています。そして、象徴的な出来事がいくつも起きた1968年という年は、そういった視点で日本の写真を見る、とても良い切り口になるのではないかと考えたわけです」
1968年というと、伝説的な写真雑誌として度々取り上げられる『プロヴォーク 思想のための挑発的資料』が創刊されていますね。
「写真というのは、ちゃんとピントがあっていて、ものの細部まできちんと写っていなければならない、それが写真の写真たるゆえんであるというのが、それまでの一般的な認識であり、近代写真の枠組みでもありました。ところが、プロヴォークの写真家たちが発信したのは、俗にいうアレ・ブレ・ボケ写真、簡単に言えば何が写っているのか分からない写真だった。つまり、近代写真が作り上げてきた枠組みを、徹底的に破壊することが彼らの最大の目的であったのではないかと思います」
 |
 |
左)『プロヴォーク』1号表紙 1968年11月1日 右)ユニット'69 「'69幻実 日本」 石川島播磨重工 1969年
『プロヴォーク 思想のための挑発的資料』
1968年11月に、中平卓馬、多木浩二、高梨豊、岡田隆彦(詩人)を同人として刊行された写真雑誌(2号より森山大道が参加)。アレ・ブレ・ボケの表現で、近代的写真表現が構築した「写真」の枠組みを根源的に問いかけた。
それがとても格好良く見えるのは、同人であった多木浩二や中平卓馬の挑発的な文章の力もありましたよね。
「まさにアジテーション(扇動)ですね。実際、中平卓馬は当時の学生運動の主要なアジテーターでもありました。結局、革命はおきなかったわけですが、学生運動に没頭した学生だけでなく、音楽や映画や演劇の世界でも、みんなそれぞれが自分たちのヴィジョンを持とうとした時代だったし、写真家もそういった大きな時代の流れの中で写真を撮っていたと言って良いと思います」

左)10.21とはなにかを出版する会 『10.21とはなにか』 1969年 右)三里塚写真の会 『三里塚』より 1971年
「写真の叛乱」
70年の安保改定を前にして学生たちは、情況を変革しようと、大学構内から路上へ、そして空港建設反対を唱える三里塚の農村まで、あらゆる場所へと叛乱してゆき、闘争は日常となった。学生や農民たちの側に立って撮影した写真群に加え、今回初めて全日本学生写真連盟の学生・OBの集団撮影行動による写真群を紹介する。集団的無名性によって撮影・発表された作品は、今なお問題を投げかける。
一方、コンポラ写真という言葉が世に出て注目されました。
「この用語の基になっているのは、1966年にアメリカで開催された「コンテンポラリー・フォトグラファーズ 社会的風景に向かって」という展覧会です。展覧会カタログが輸入されて、私的な視点で世界を撮るという写真のあり方が注目され、リー・フリードランダーなどの表現が話題になりました。そして、1968年に雑誌『カメラ毎日』で、このような写真が取り上げられたわけですが、この時、コンポラ写真という言葉もメディアで最初に使われたようです」
日本のコンポラ写真の特徴はどんなものですか?
「問題になるのは、日常性、私性というものではないかと思っています。プロヴォークの写真を、何が写っているのか分からない写真であったとするならば、コンポラ写真は、何が写っているのかは分かるけれども、何を撮ったのか分からない写真と言えるかもしれません」
 |
牛腸茂雄 シリーズ「日々」より 1967-70年
「コンポラ写真」
コンテンポラリー・フォトグラファーズ 社会的風景にむかって」(1966年12月 ジョージ・イーストマン・ハウス国際写真博物館)の写真表現と共通する、現実への態度を持つ日本の若い写真家たちの動向を、大 清司が「コンポラ写真」と紹介した(『カメラ毎日』1968年6月)。日常への私的なまなざしを特徴とする写真表現は、若い世代の写真家たちに「写真」の新しい可能性をもたらした。
つまり、あまりに日常的なものが写っているがゆえに、写真の意図が分からない、ということですね。それまで、作品として日常を写真に撮るということはあまりなかったのでしょうか?
「普段生活している中で見ている何気ない光景を撮るということはまずなかったし、荒木経惟が1971年に発表した「センチメンタルな旅」のように、自身の新婚旅行をそのまま赤裸裸に全部撮るなんてことはあり得ませんでした。しかも、それこそが写真だと荒木は言ったわけです。新婚旅行の写真は私の愛のそのものである、これこそが写真であり、それ以外は全部嘘っぱちだ、というわけです」
お話をうかがっていると、当時の写真の動向が、まるでロックやフォークソング、ニューミュージックといった音楽の流れと重なって見えてきます。
「まさに、そんなふうにとらえてもらっても良いと僕は思っています。荒木経惟の作品から感じる気分が、井上陽水の「傘がない」を聴く時のそれととてもよく似ているというのは、決して否定できない感覚だと思うし、この写真を撮っていた人たち、この写真を見ていた人たちはみんな、私たちと同じように音楽を聴き、映画をみ、小説を読み、演劇を観ていたわけですから」
時代とともに立ち上がってくるのが写真だということなんですね。
「変な言い方だけど、展覧会を見終わって時代の気分だけでも分かってもらえれば良いんじゃないかと思っています。学生運動の写真を格好良いとみられてしまうのは、当時、その中にいた人たちからすればとんでもない、俺たちはこの写真を撮るために命をはっていたんだと言われるかもしれない。でも、時を経た今の時代の人々が、そういう写真を観て、熱い時代だなって思う、これもまた正直な気持ちだと思う。そこから興味を持って、更に先に進んで考えてもらえるきっかけになれば、本展は大成功だと思っています」
「日本写真の1968」展 展覧会情報はこちら