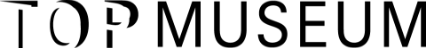トピックス

《海を見る》、シリーズ〈陽と骨〉より 1976年
《明日を見る家族》、シリーズ〈陽と骨〉より 1974年

たとえ写真家の名を知らなくても、誰でも一度ならず彼の写真を見たことがあるのではないだろうか。1970~80年代には、日産のフェアレディZ、ソニーの"ジャッカル"、サントリーの"オールド"の広告写真や、井上陽水、大江健三郎のポートレートなど、操上和美は世に広く知られる傑作を数多く手がけてきた。そんな写真界の鬼才が、50年以上、日常的に撮り続けてきた作品群で個展を開催する。『陽と骨』『陽と骨Ⅱ』『NORTHERN』『Diary』など、本展に出展予定の作品や、写真に対する思いを語ってもらった。
 |
 |
《夢を見る猫》、シリーズ〈陽と骨〉より 1979年
1960~70年代は以後の方向を決定づけるようなインパクトのある写真がたくさん出てきた時代です。操上さんは1961年に東京綜合写真専門学校を卒業された後、『住まいと暮らしの画報』編集部を経てセントラルスタジオの杉木直也氏に師事されたのですね?
「当時、『洋酒天国』というサントリーの機関誌があって、それを作家の開高健さんやイラストレーターの柳原良平さんと一緒に制作していた杉木直也さんが、新しくスタジオを設立するということで紹介していただき、アシスタントとして入社したんです。普通は入社してすぐには撮らせてはもらえませんが、セントラルスタジオでは写真家が杉木さんと僕の二人だけだったから、僕も会議から参加させてもらって、良い企画を出せば、どんどん撮らせてもらえるという環境でした。今思えばずいぶん生意気だったと思いますけど、北海道を出て上京した時には故郷を捨てるくらいの覚悟だったし、若くて気もはやっていたから、臆せずにどんどん意見を出していましたね。そこでは写真だけではなく、企画やビジュアル全体から発想する考え方とか、コピーライティングと写真の両方から見る視点など、広告写真の基礎を学んだと思います」
65年に独立されましたが、写真のみならず、企画・演出・コピー、そして映像制作までひとりで手がける写真家は大変少なかったとうかがいました。
「初めて仕事で撮影した映像が、ミツワ石鹸のCMでした。まだモノクロ映像でしたから綺麗に映らないという理由で白い泡はダメ、もちろん女性の裸も当然NGという時代でしたが、あえてそれに挑戦したんです。泡風呂から女性がサッと立ち上がった瞬間にバスタオルでまかれるという内容で、もちろん裸は映ってはいないんですが(笑)、それが大ヒットした。操上だったら全部一人に任せられるということになり、一気に仕事が増えて忙しくなったんです。
その時、このままだと自分の写真も撮れずに終わるのではないかという危機感を感じて、常日頃からスナップを撮るようになったんです。寝る時間もないくらいでしたが、海外への移動途中とかロケの合間に写真を撮っていました。それが自分の運動であり、感覚のトレーニングだと思っていたわけです。写真家なんだから写真を絶対に自分から離さないという気持ちが強かったですね。
写真を撮ることは、見たり触ったりすることと同じように、自分の体の内に持っている生理感覚で行う行為なので、広告写真だろうがドキュメンタリーだろうが感覚的には同じです。
(一般に)受ければ良いということではなくて、自分は何を触りたいのか、何に興味があるのかということから発想するわけです」
 |
 |
《冬の庭》、シリーズ〈NORTHERN〉より 2012年1月
デジタル技術が出てきたことで感じる変化はありますか?
「広告などの場合、アナログのカメラだとフィルムがなくなったら間髪入れずに次のカメラに持ち替えて、最後まで被写体とのセッションを途切れさせずに終えられますが、デジタルカメラだとどうしても撮影中に撮った画像を確認してしまうんですね。時には、カメラをケーブルでつないで画像をモニタに出し、アートディレクターとかクライアントなど、撮られている本人も含めて、全員で見たりもする。すると作業も止まるし、テンションも下がってしまう。つまり、攻め込みが足りなくなってしまうんです。僕は、技術の違いというよりも、そういう時間や撮影中の緊張感のあり方が変わってしまうことのほうが、影響を大きく感じますね」
1970年より撮りためてきた写真から357点を選んでまとめた作品集『Diary』(2005年)は、印刷ではなくコピー機を使って製本されていますね?
「いわば日記のようなものですから、豪華なものを作ろうという発想はもともとなくて、試しに自分の家にある古いコピー機でやってみたら、すごく良かった。コピー用紙は時間が経つとだんだん剥げて色あせてくるから、それがいかにも古い日記帳みたいになったんです。ところが、今のコピー機は進化していて、コピーだか印刷だかわからないくらい綺麗なんですよ。だから、わざわざ悪くなるように機械操作をして、質の悪いコピーをとったんです」
普段使いのカメラや玩具カメラで日常を撮影した「陽と骨」(1984年)の第二弾として、ポラロイドSX-70で撮影した写真をまとめた作品集「陽と骨Ⅱ」を昨年に発刊されました。
「カメラは何でも良いんです。1ドルくらいの玩具カメラで撮った写真のほうが、高性能なカメラで撮った写真よりずっとインパクトが出て良くなることがある。たとえ印画紙やフィルムがなくなったとしても、自分の写真は撮れる自信があるし、自分の感覚さえ衰えなければ良いことだと思っています」
では、プリントする時の暗室作業はどんな感覚なんですか?
「現像してみると、自分が愛して撮ったものがそっくりそのまま浮かび上がってきて感動することもあるし、逆にあんなに手応えがあったのに、全然だめだという時もある。だから、暗室は反省する場所でもあるし、夢見る場所でもありますね。また、なかなか思い通りにならなければ、やり方を思いきり変えてみると、一気に良くなるときもあるんですよ。暗室作業は、自分でやったほうが絶対楽しいし、もう一歩前に行けるプロセスだと思います」
 |
 |
今回の展覧会タイトルにはどんな思いが込められているのでしょうか?
「長いタイトルでしょ(笑)。時間について考えてみると、鉄でさえ腐食して錆びていくわけですから、生物だろうが事物だろうが、みんな自分の時間を持って存在しています。そういう意味で、現在は死に向かう旅の過程にあるとも言える。だから、自分が撮った写真は「時のポートレート」だと勝手に思っているんです。加えて、全てのものは写真になることによって、もう一つ違う写真としての時間を所有することにもなるわけです。しかも、写真のほうが長生きするかもしれない。そういう時間のずれのようなことを考えると、生きている我々の存在がノスタルジックなものにも思えてくる。懐かしいという意味ではなく、そういう現実と写真の時間がずれていく感覚をこの展覧会のタイトルには込めたつもりだし、観ていただく方々が写真そのものや僕の作品について考える糸口になれば良いなと思っています」
聞き手:丹羽晴美(東京都写真美術館学芸員) 構成:富田秋子
2012年4月インタビュー
展覧会詳細はこちらから