総合開館30周年記念スペシャル
【アーカイブ】「鷹野隆大 カスババ―この日常を生きのびるために―」展 スペシャルインタビュー:鷹野隆大(出品作家)
東京都写真美術館は今年、総合開館から30周年を迎えました。その特別な一年の最初を飾る展覧会が「鷹野隆大 カスババ―この日常を生きのびるために―」。鷹野さんは1994年の初個展から、セクシュアリティと身体、都市と日常、写真の原理など、わたしたちが見て見ぬふりをしているもの、見過ごしてしまっているものへの関心を呼び起こす作品を発表してきました。本展がどのようなものになるのか、その思いと構想についてお話をうかがいました。
東京都写真美術館ニュース「アイズ」120号掲載
インタビュー:タカザワケンジ
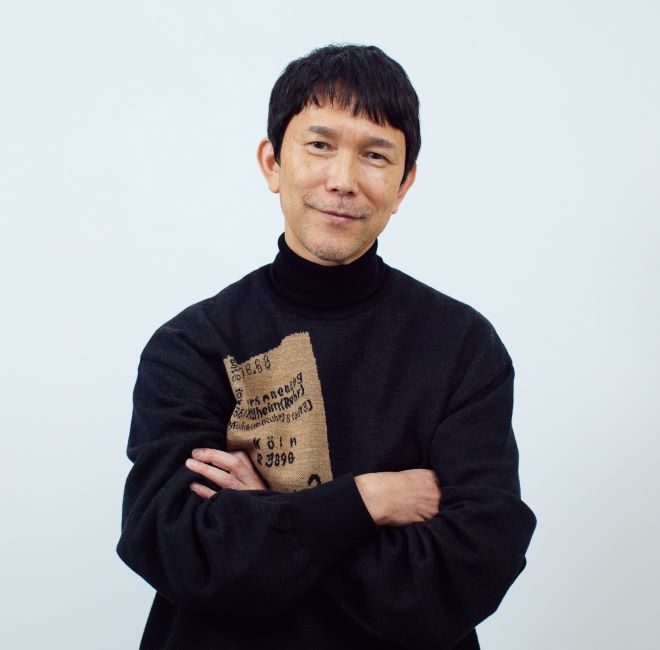 鷹野隆大 撮影:藤澤卓也
鷹野隆大 撮影:藤澤卓也
──まず本展の構想がどのようにつくられたかからお聞かせください。
鷹野■最初に考えたのは写真ならではのイメージ性をうまく提示できないかということでした。写真表現はいま、作品の背景にある物語と結びつけて展示されることが多いと思うんです。この写真はこういう流れの中の一枚ですよ、と。しかし、今回は写真それぞれを独立させて、ポンとイメージだけがあるという状態で展示できないかと考えました。
会場全体のイメージは「都市」。都市空間にはさまざまな偶然の出会いがあります。見てくださった方たちがそれぞれのイメージと出会い、対話していただければと思っています。
──都市と言えば、メインタイトルでもある〈カスババ〉が思い浮かびます。カスババは鷹野さんの造語で、都市の中のカスのような場(複数形)を撮ったシリーズです。もう 20年以上続けているんですよね。
鷹野■東京で暮らしていると、日々の生活の中で、写真を撮る気をなくさせるような、どうしようもなく退屈な場所が至るところにあって、なるべく見ないようにしてきたんですが、あるとき、最も身近なものを自分は無きものにしようとしているのではないかと思いました。それは存在するものを存在しないかのように扱う暴力的な行為ではないかと。だったら、それに向き合ってみなければ、と思い直して撮り始めたのがきっかけです。カスだと思ったら何も考えずに撮るようにしましたが、何のモチベーションも湧かないものに向けてシャッターを切るのは正直言って苦痛でした。オートフォーカスのコンパクトカメラだからできたんだと思います。ピントを合わせるという作業が必要だったら、そこで気持ちが折れて続けられなかったかもしれません。
 鷹野隆大《2015.10.28.#a28》〈カスババ2〉より 2015年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
鷹野隆大《2015.10.28.#a28》〈カスババ2〉より 2015年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
──撮りためていく中で〈カスババ〉について気づかれたことはありますか。
鷹野■撮っている時にはよくわからなかったんですが、2010年に写真集を出すことになり、写真を見直した時に気づいたのが、ポイントがない場所だということ。写真を撮るという意識を持って歩いていると、どうしても撮るべきポイントを探してしまうんですね。カスババにはポイントがないから、目がぐるぐるとさまよう。収まりどころがない。そういう状態が不愉快だし、イライラさせるんだと思いあたりました。
──それでも撮り続けた。写真集が出た後も続けていて、2冊目の写真集が出るそうですね。
鷹野■ある時期、写真はもう終わったのかなと思ったことがありました。動画の解像度が一気に上がった頃です。解像度が十分あるなら、写真は動画から静止画を切り出せばそれで済むんじゃないかと。でも、実際に試してみるとうまくいかない。動画から切り出すのでは得られないイメージの現れが写真にはあるんです。写真を撮るということは、その現れを求めることなんじゃないだろうかと気づきました。そのこととカスババを結びつけて考えてみよう。そう思ってつくったのが『カスババ』の続編です。前作は2001年から2010年に撮ったもので、今作は2011年から2020年となっています。この展覧会に合わせたタイミングで出版します。
──〈カスババ〉は鷹野さんにとって写真とは何かを考える場なんですね。
鷹野■はい、今回2冊目を出すにあたって、10年ごとの研究発表みたいなものかなぁと感じています。それと、〈カスババ〉シリーズはそもそも、「毎日写真」という毎日必ず一枚は写真を撮るプロジェクトの中から選び出した写真で構成されているのですが、この「毎日写真」自体が写真について考える場になっています。

鷹野隆大《2012.08.12.#b30》〈毎日写真〉より 2012年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
──本展は東京都写真美術館が総合開館30周年を迎えた記念展の第一弾です。東京都写真美術館にどのような印象をお持ちですか。
鷹野■写真について考える機会を与えてくれる美術館ですね。19世紀の古典作品から新進作家まで、時代とともに写真という媒体と並走してきている美術館だと思います。
とくに最近は古典的な写真について考えることが多いので、古い作品のコレクション展には刺激を受けますね。古典的な写真を見ることは写真が生まれた時代背景を考えることであり、写真が帯びている近代性を確認する作業でもあります。そしてそれはわたしにとって、何が写真を写真たらしめているのかを探る機会でもあります。
──写真誕生の昔にさかのぼると言えば、本展で展示される〈Sun Light Project〉でソルトプリント(単塩紙[塩化銀紙])という19世紀の写真発明当時の技法を使っていますね。近年、取り組まれている「影」をテーマにしたシリーズのひとつです。
鷹野■写真について考えるうえで光と影は欠かせませんが、わたしはとくに影に興味があります。しかも「影の写真」ではなく、影そのものを写真にできないかと考えるようになりました。〈Sun Light Project〉はその試みのひとつで、太陽光によってできる影を採集しようとした作品です。普通の印画紙では性能が良すぎてあっという間に真っ黒になってしまうので、低感度のものはないかと考えているうちに、ある意味原始的な技法にたどりつきました。 ところが、こっちはこっちで感度が低すぎて、30秒ぐらい露光が必要なんですね。それで、影の輪郭がぼやけてしまうんです。その点でも難しかったです。でも、市販の印画紙ではなく感光材料を紙に塗るところから始めるので、写真の原理に触れているようで面白いんです。

左:鷹野隆大《2021.04.11.Ps.#03》〈Sun Light Project〉より 2021年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
右:鷹野隆大《2019.12.31.P.#02(距離)》〈Red Room Project〉より 2019年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
──写真の歴史をさかのぼる一方で、〈カスババ〉や〈毎日写真〉のように現代の東京や都市空間を主題にした作品もありますね。第31回木村伊兵衛写真賞を受賞した『IN MY ROOM』は部屋に人物を招いて撮影したポートレイトのシリーズですが、都会だからこそ成立する、都市の写真でもあると思います。
鷹野■部屋の雰囲気が多少でていますが、ある種の抽象化された空間なので、そこで現代の都市のあり方と結びつくかもしれません。
──ミニマルな空間から一歩外に出ると、カオスな世界が広がる。それが〈カスババ〉だと言えるのかも。
鷹野■東京の街はごちゃごちゃに見えますが、汚くしようと思ってそうなったわけではなく、それぞれが良かれと思った結果なんですよね。このまとまりのなさが東京の特徴で、それが日本の都市空間の特徴でもある。わたし自身はそういう東京をヨソ者として撮っているんだと思います。東京出身ではないので、木村伊兵衛とか 荒木(経惟)さんのような東京出身の写真家たちとは東京との関わり方が違うと思いますね。
──〈In My Room〉のようなセクシュアリティと身体をテーマにしたシリーズでは、〈おれと〉の作品も展示されるそうですね。
鷹野■〈おれと〉は被写体となってくれた方とわたしが裸で記念写真を撮るシリーズなんですが、自分としては今の社会情勢との兼ね合いもあって、今回はぜひ出したいと思っていました。
──社会情勢というのは、世界で紛争や政治不安が止まない状況でしょうか。
鷹野■はい、このような時代、状況だからこそ、今回は思い切って、これまで展示できなかった作品を出そうと思いました。つまり、議論のある作品を出しづらい状況に抵抗すべき時であるような気がしたのです。いままでわたしは正面切ってこういうことを表明して来なかったのですが、この状況では鷹揚にはしていられないなと。
わたし自身は写真という表現媒体に出会ったとき、自分の居場所を得た気がしました。自分を現す手段を手にするかどうかは、その後の人生でとても大きなことだったと振り返って思います。そしてそれを自分の解放区とするためには、ときに闘うことも避けられません。ところがいま、世の中全体が自分で枠をつくってそこからはみ出さないようにしているような気がします。居場所は人が与えてくれるものではないので、待っているとどんどん狭まっていきます。わたしは大学で日々学生と接していますが、彼らにも自分の居場所を作ることの可能性を感じてもらえたらいいなと思います。

鷹野隆大 《2002.09.08.M.#b08》〈立ち上がれキクオ〉より 2002年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
鷹野隆大
1963 年福井県生まれ。セクシュアリティをテーマに1994年より作家活動を開始。2006年、写真集『IN MY ROOM』で第31回木村伊兵衛写真賞を受賞。毎日欠かさず撮ることを自らに課したプロジェクト〈毎日写真〉を 1998 年に開始し、その中から日本特有の無秩序な都市空間の写真を集めた『カスババ』を2011年に発表。その後、東日本大震災を機に影をテーマに様々な作品制作に取り組んでいる。2021年、個展「鷹野隆大 毎日写真 1999-2021」(国立国際美術館、大阪)を開催。2022年、第72回芸術選奨文部科学大臣賞受賞(美術部門)、第38回写真の町東川賞国内作家賞受賞。
総合開館30周年記念 鷹野隆大 カスババ ―この日常を生きのびるために―
2025年2月27日(木)~6月8日(日)
東京都写真美術館 2階展示室
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4820.html
東京都写真美術館ニュース「アイズ」120号掲載
インタビュー:タカザワケンジ
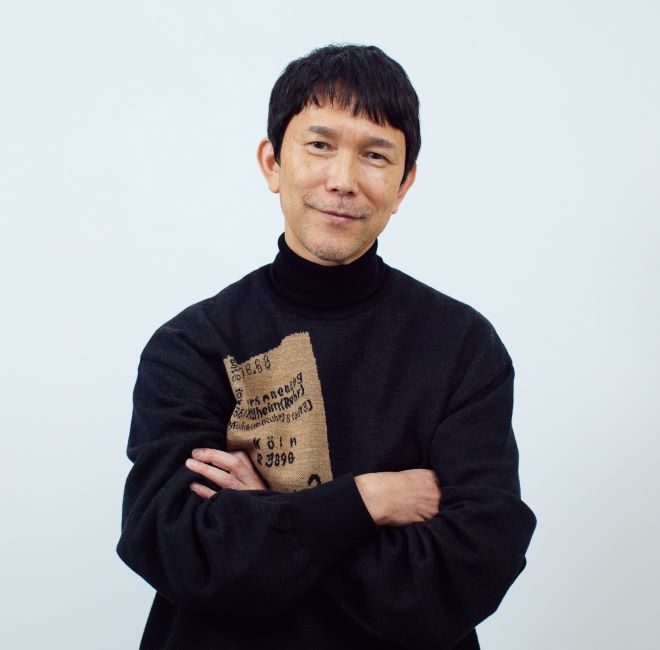
──まず本展の構想がどのようにつくられたかからお聞かせください。
鷹野■最初に考えたのは写真ならではのイメージ性をうまく提示できないかということでした。写真表現はいま、作品の背景にある物語と結びつけて展示されることが多いと思うんです。この写真はこういう流れの中の一枚ですよ、と。しかし、今回は写真それぞれを独立させて、ポンとイメージだけがあるという状態で展示できないかと考えました。
会場全体のイメージは「都市」。都市空間にはさまざまな偶然の出会いがあります。見てくださった方たちがそれぞれのイメージと出会い、対話していただければと思っています。
──都市と言えば、メインタイトルでもある〈カスババ〉が思い浮かびます。カスババは鷹野さんの造語で、都市の中のカスのような場(複数形)を撮ったシリーズです。もう 20年以上続けているんですよね。
鷹野■東京で暮らしていると、日々の生活の中で、写真を撮る気をなくさせるような、どうしようもなく退屈な場所が至るところにあって、なるべく見ないようにしてきたんですが、あるとき、最も身近なものを自分は無きものにしようとしているのではないかと思いました。それは存在するものを存在しないかのように扱う暴力的な行為ではないかと。だったら、それに向き合ってみなければ、と思い直して撮り始めたのがきっかけです。カスだと思ったら何も考えずに撮るようにしましたが、何のモチベーションも湧かないものに向けてシャッターを切るのは正直言って苦痛でした。オートフォーカスのコンパクトカメラだからできたんだと思います。ピントを合わせるという作業が必要だったら、そこで気持ちが折れて続けられなかったかもしれません。

鷹野■撮っている時にはよくわからなかったんですが、2010年に写真集を出すことになり、写真を見直した時に気づいたのが、ポイントがない場所だということ。写真を撮るという意識を持って歩いていると、どうしても撮るべきポイントを探してしまうんですね。カスババにはポイントがないから、目がぐるぐるとさまよう。収まりどころがない。そういう状態が不愉快だし、イライラさせるんだと思いあたりました。
──それでも撮り続けた。写真集が出た後も続けていて、2冊目の写真集が出るそうですね。
鷹野■ある時期、写真はもう終わったのかなと思ったことがありました。動画の解像度が一気に上がった頃です。解像度が十分あるなら、写真は動画から静止画を切り出せばそれで済むんじゃないかと。でも、実際に試してみるとうまくいかない。動画から切り出すのでは得られないイメージの現れが写真にはあるんです。写真を撮るということは、その現れを求めることなんじゃないだろうかと気づきました。そのこととカスババを結びつけて考えてみよう。そう思ってつくったのが『カスババ』の続編です。前作は2001年から2010年に撮ったもので、今作は2011年から2020年となっています。この展覧会に合わせたタイミングで出版します。
──〈カスババ〉は鷹野さんにとって写真とは何かを考える場なんですね。
鷹野■はい、今回2冊目を出すにあたって、10年ごとの研究発表みたいなものかなぁと感じています。それと、〈カスババ〉シリーズはそもそも、「毎日写真」という毎日必ず一枚は写真を撮るプロジェクトの中から選び出した写真で構成されているのですが、この「毎日写真」自体が写真について考える場になっています。

鷹野隆大《2012.08.12.#b30》〈毎日写真〉より 2012年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
──本展は東京都写真美術館が総合開館30周年を迎えた記念展の第一弾です。東京都写真美術館にどのような印象をお持ちですか。
鷹野■写真について考える機会を与えてくれる美術館ですね。19世紀の古典作品から新進作家まで、時代とともに写真という媒体と並走してきている美術館だと思います。
とくに最近は古典的な写真について考えることが多いので、古い作品のコレクション展には刺激を受けますね。古典的な写真を見ることは写真が生まれた時代背景を考えることであり、写真が帯びている近代性を確認する作業でもあります。そしてそれはわたしにとって、何が写真を写真たらしめているのかを探る機会でもあります。
──写真誕生の昔にさかのぼると言えば、本展で展示される〈Sun Light Project〉でソルトプリント(単塩紙[塩化銀紙])という19世紀の写真発明当時の技法を使っていますね。近年、取り組まれている「影」をテーマにしたシリーズのひとつです。
鷹野■写真について考えるうえで光と影は欠かせませんが、わたしはとくに影に興味があります。しかも「影の写真」ではなく、影そのものを写真にできないかと考えるようになりました。〈Sun Light Project〉はその試みのひとつで、太陽光によってできる影を採集しようとした作品です。普通の印画紙では性能が良すぎてあっという間に真っ黒になってしまうので、低感度のものはないかと考えているうちに、ある意味原始的な技法にたどりつきました。 ところが、こっちはこっちで感度が低すぎて、30秒ぐらい露光が必要なんですね。それで、影の輪郭がぼやけてしまうんです。その点でも難しかったです。でも、市販の印画紙ではなく感光材料を紙に塗るところから始めるので、写真の原理に触れているようで面白いんです。

左:鷹野隆大《2021.04.11.Ps.#03》〈Sun Light Project〉より 2021年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
右:鷹野隆大《2019.12.31.P.#02(距離)》〈Red Room Project〉より 2019年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
──写真の歴史をさかのぼる一方で、〈カスババ〉や〈毎日写真〉のように現代の東京や都市空間を主題にした作品もありますね。第31回木村伊兵衛写真賞を受賞した『IN MY ROOM』は部屋に人物を招いて撮影したポートレイトのシリーズですが、都会だからこそ成立する、都市の写真でもあると思います。
鷹野■部屋の雰囲気が多少でていますが、ある種の抽象化された空間なので、そこで現代の都市のあり方と結びつくかもしれません。
──ミニマルな空間から一歩外に出ると、カオスな世界が広がる。それが〈カスババ〉だと言えるのかも。
鷹野■東京の街はごちゃごちゃに見えますが、汚くしようと思ってそうなったわけではなく、それぞれが良かれと思った結果なんですよね。このまとまりのなさが東京の特徴で、それが日本の都市空間の特徴でもある。わたし自身はそういう東京をヨソ者として撮っているんだと思います。東京出身ではないので、木村伊兵衛とか 荒木(経惟)さんのような東京出身の写真家たちとは東京との関わり方が違うと思いますね。
──〈In My Room〉のようなセクシュアリティと身体をテーマにしたシリーズでは、〈おれと〉の作品も展示されるそうですね。
鷹野■〈おれと〉は被写体となってくれた方とわたしが裸で記念写真を撮るシリーズなんですが、自分としては今の社会情勢との兼ね合いもあって、今回はぜひ出したいと思っていました。
──社会情勢というのは、世界で紛争や政治不安が止まない状況でしょうか。
鷹野■はい、このような時代、状況だからこそ、今回は思い切って、これまで展示できなかった作品を出そうと思いました。つまり、議論のある作品を出しづらい状況に抵抗すべき時であるような気がしたのです。いままでわたしは正面切ってこういうことを表明して来なかったのですが、この状況では鷹揚にはしていられないなと。
わたし自身は写真という表現媒体に出会ったとき、自分の居場所を得た気がしました。自分を現す手段を手にするかどうかは、その後の人生でとても大きなことだったと振り返って思います。そしてそれを自分の解放区とするためには、ときに闘うことも避けられません。ところがいま、世の中全体が自分で枠をつくってそこからはみ出さないようにしているような気がします。居場所は人が与えてくれるものではないので、待っているとどんどん狭まっていきます。わたしは大学で日々学生と接していますが、彼らにも自分の居場所を作ることの可能性を感じてもらえたらいいなと思います。

鷹野隆大 《2002.09.08.M.#b08》〈立ち上がれキクオ〉より 2002年 ©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
鷹野隆大
1963 年福井県生まれ。セクシュアリティをテーマに1994年より作家活動を開始。2006年、写真集『IN MY ROOM』で第31回木村伊兵衛写真賞を受賞。毎日欠かさず撮ることを自らに課したプロジェクト〈毎日写真〉を 1998 年に開始し、その中から日本特有の無秩序な都市空間の写真を集めた『カスババ』を2011年に発表。その後、東日本大震災を機に影をテーマに様々な作品制作に取り組んでいる。2021年、個展「鷹野隆大 毎日写真 1999-2021」(国立国際美術館、大阪)を開催。2022年、第72回芸術選奨文部科学大臣賞受賞(美術部門)、第38回写真の町東川賞国内作家賞受賞。
総合開館30周年記念 鷹野隆大 カスババ ―この日常を生きのびるために―
2025年2月27日(木)~6月8日(日)
東京都写真美術館 2階展示室
https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4820.html
